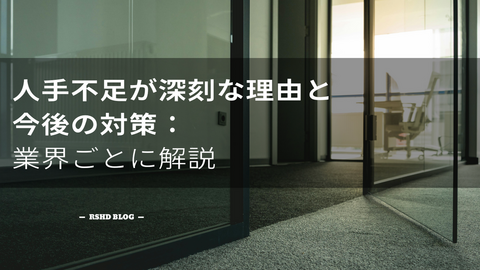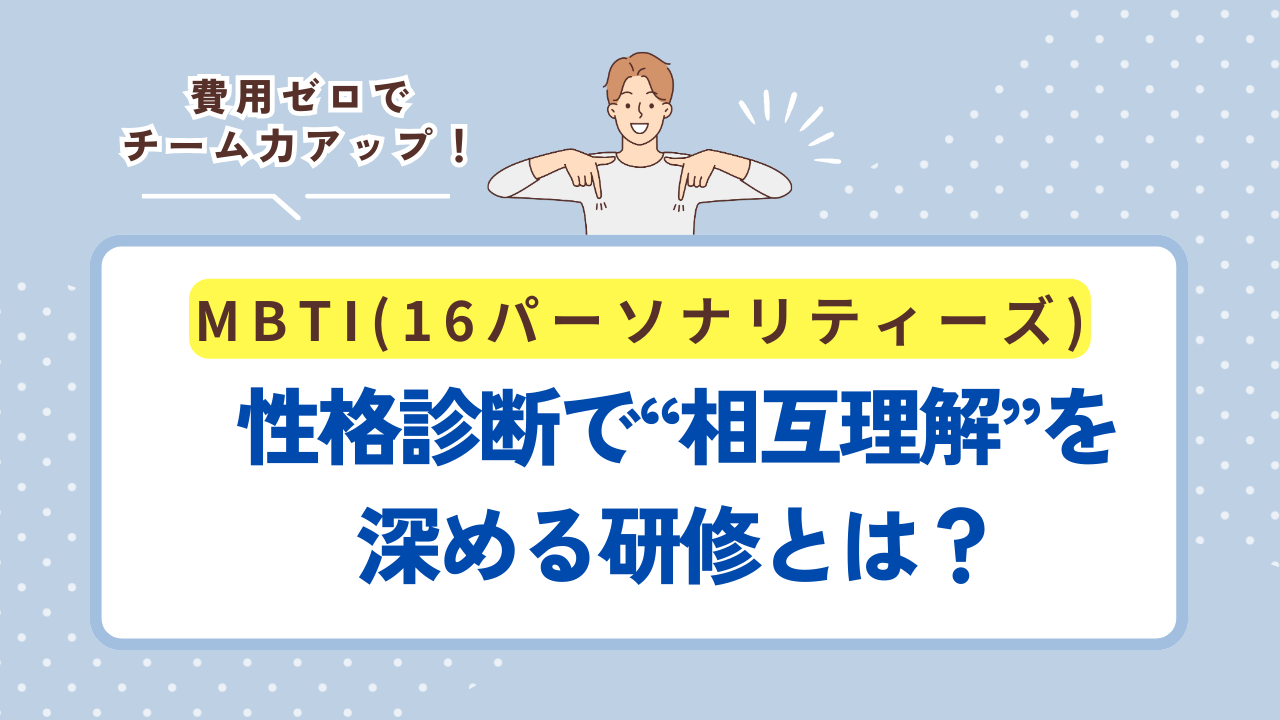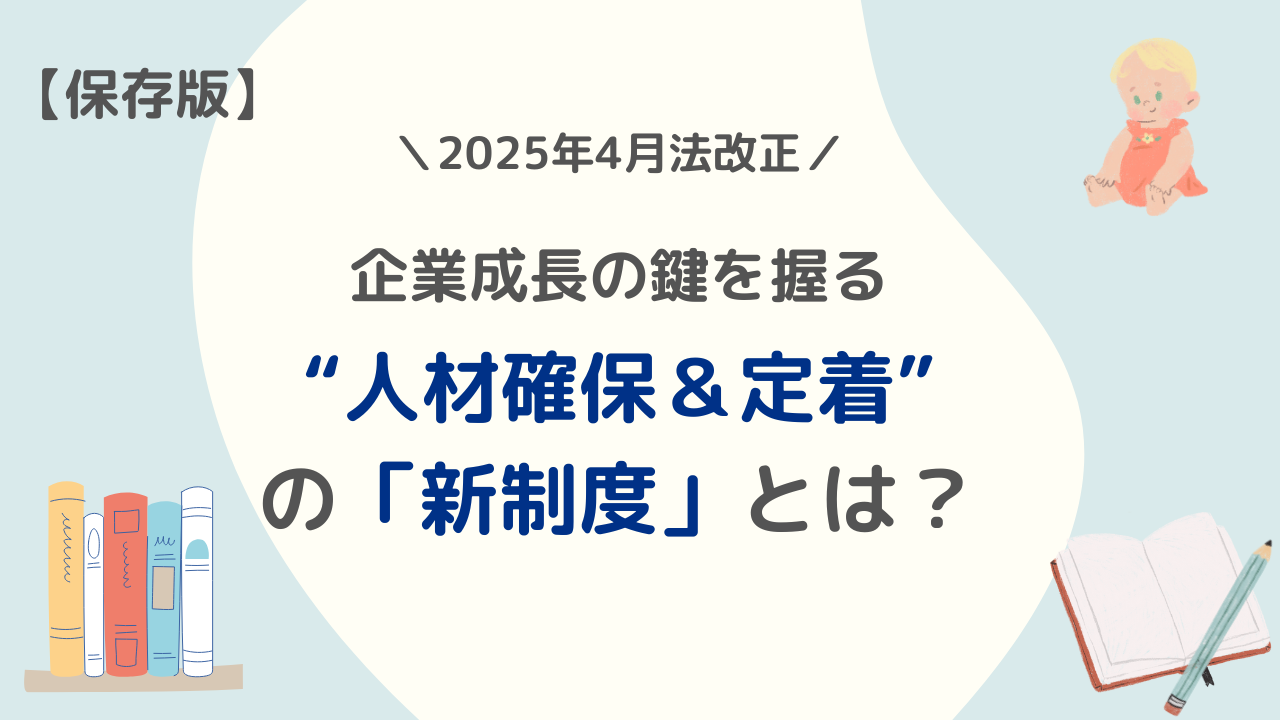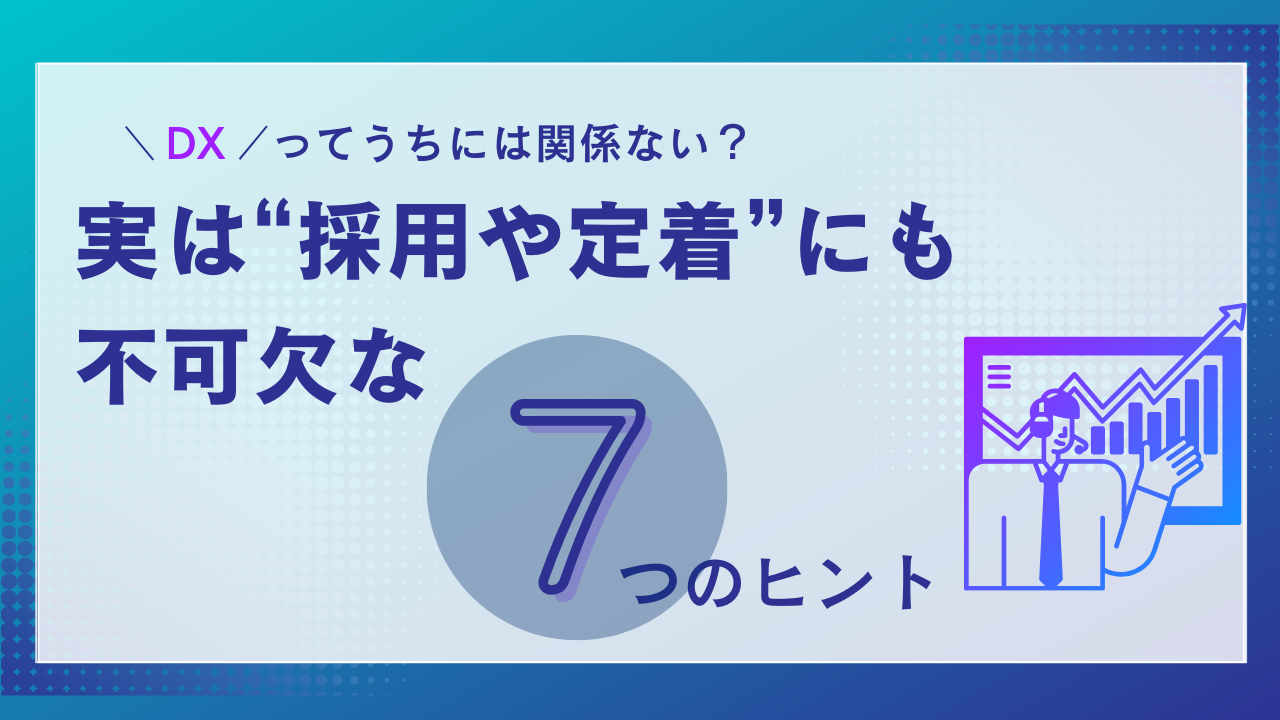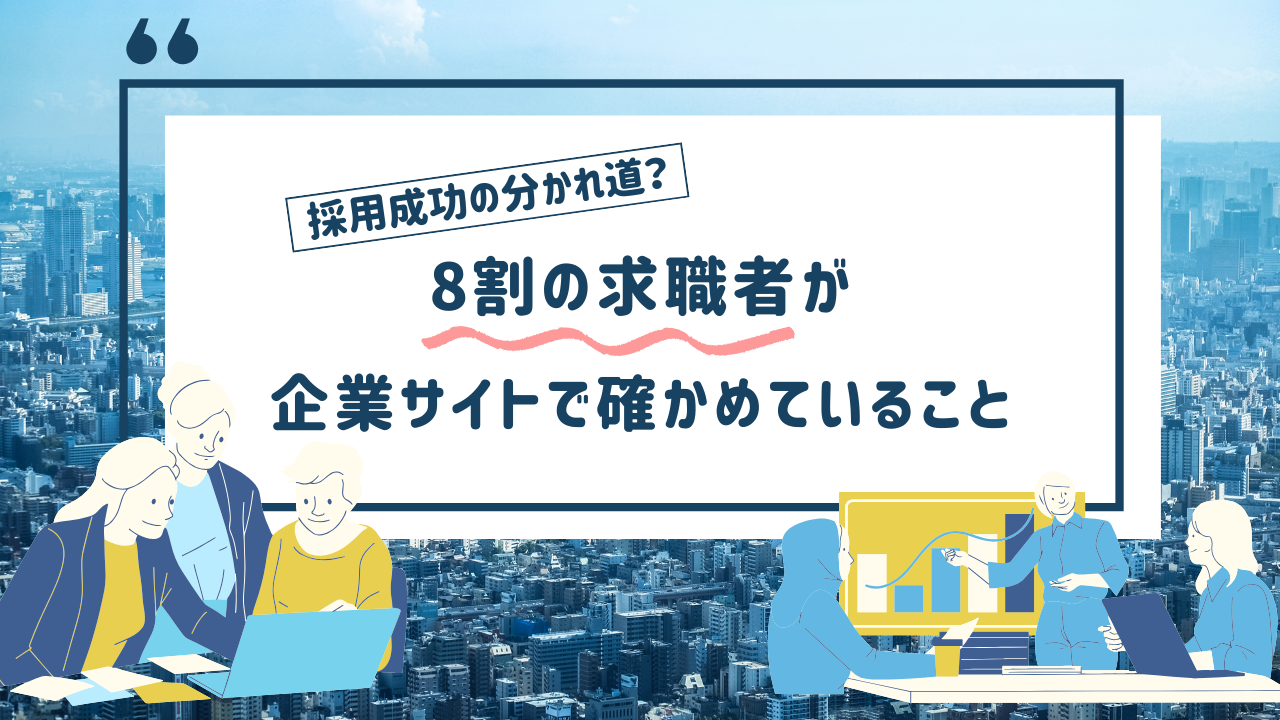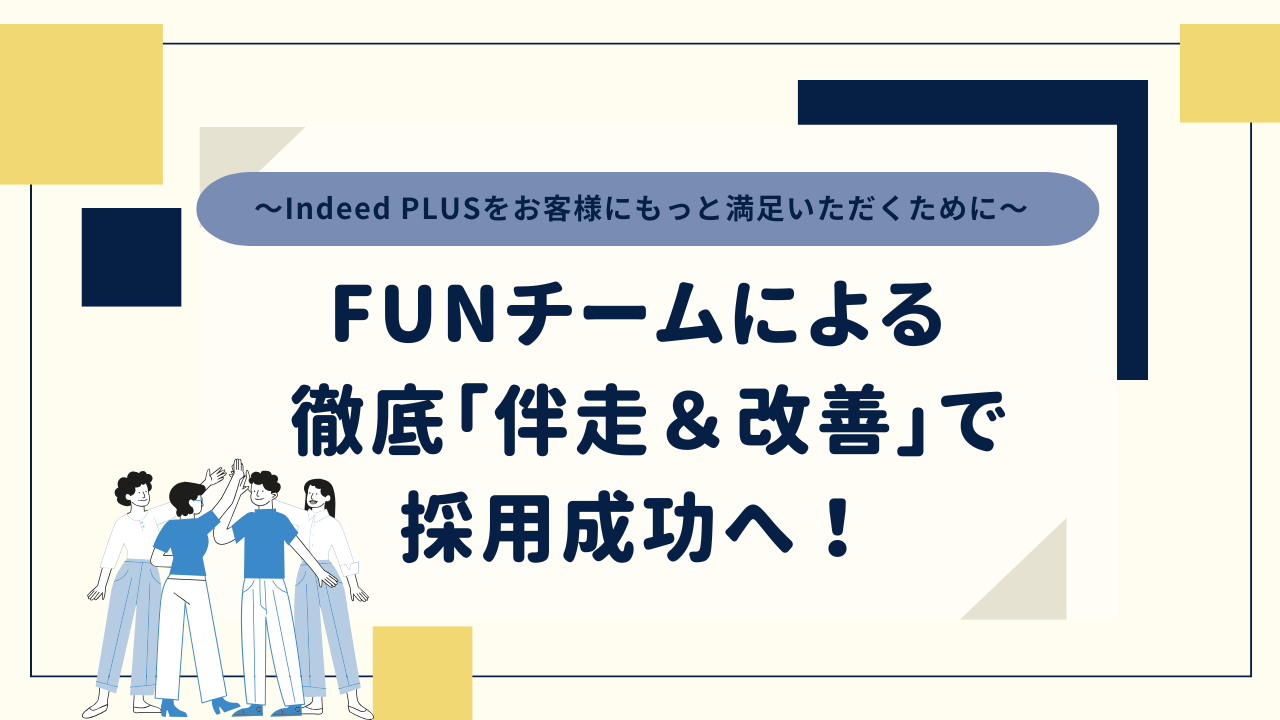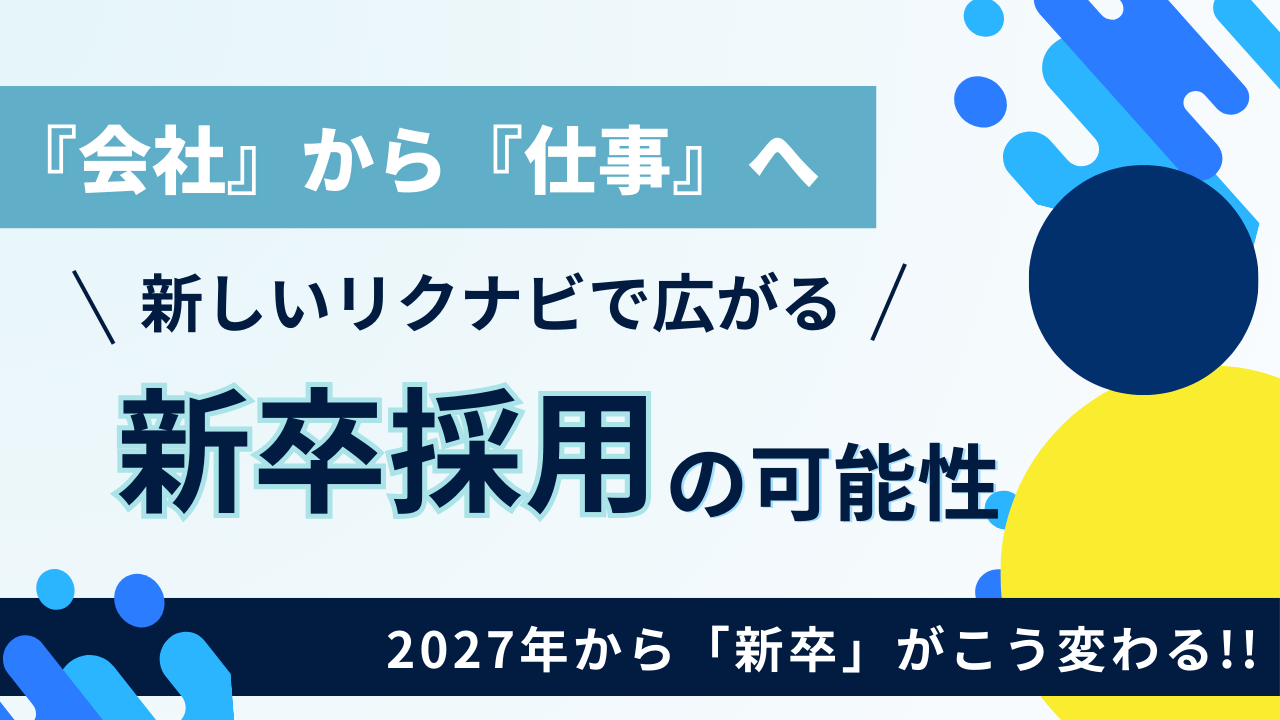公開日: 2025年03月17日 / 更新日: 2025年03月18日
ロケスタ通信採用支援
人材育成の重要性と最新トレンド:企業研修戦略とDX人材育成のポイント

現代のビジネス環境において、人材育成は企業の成長と競争力強化になくてはならない経営戦略の一つです。企業が将来にわたって持続的に発展するためには、社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、必要なスキルを身につけてもらうことが重要です。人材育成は、企業の未来をつくるもの。
この記事では、人材育成の重要性と最新トレンドから始め、効果的な研修プログラムの方法、リーダーシップ開発や人材マネジメントのポイント、さらにデジタルスキル・DX(デジタルトランスフォーメーション)対応人材の育成まで、解説します。
目次
- 人材育成が注目される背景
- 人材育成の最新トレンド
- リスキリング(Re-skilling)
- 職場外研修(Off-JT)からオンライン研修へ
- OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)偏重から計画的育成へ
- 人材育成に関する企業課題の顕在化
- 次世代リーダー育成への関心
- 主な人材育成手法とその特徴
- OJT(On-the-Job Training) – 職場内教育
- Off-JT(Off-the-Job Training) – 職場外研修
- 自己啓発(Self Development) – 自発的学習
- メンター制度・コーチング・1on1ミーティング – 対話型の育成支援
- その他の手法
- 効果的な研修プログラムの設計と実施のポイント
- 経営方針・育成理念の共有
- 人材育成ニーズの把握(現状分析)
- 育成目標と方針の策定
- 研修計画の立案(プランニング)
- 研修の実施(Do)
- 効果測定とフォローアップ(Check & Act)
- 環境・風土づくり
- 外部リソース・助成制度の活用
- リーダーシップ開発のポイント
- ハイポテンシャル人材の選抜と育成計画
- ストレッチアサイン(高チャレンジな任務付与)
- リーダーシップ研修・トレーニング
- メンタリングとロールモデル
- 360度フィードバックと自己認識
- 継続的なリーダーシップ経験
- 人材マネジメント上のポイント
- デジタルスキル・DX対応人材の育成
- DX人材を育成するための施策
- 人材育成の今後
- 企業が取るべきアクション
- まとめ
人材育成が注目される背景
「人材育成」とは、企業が業績向上や経営目標の達成に向けて、社員に必要なスキルや能力の習得を促す取り組みのことです。
かつては人材育成は人事部門だけの役割だと考えられがちでしたが、現在では現場も巻き込み、経営戦略と一体化して取り組む必要性が認識されています。
企業の成長を支えるのは最終的に「人」であり、人材の能力開発なくして持続的成長は望めません。特にビジネス環境の変化が激しい現代では、社員のスキル向上やキャリア開発を適切に支援できるかどうかが企業の競争力を左右します。
近年、人材育成の重要度が飛躍的に高まっている背景には、主に次のような要因があります。
技術革新と市場環境の変化
テクノロジーの進化により製品やサービスのコモディティ化が進み、技術力や価格だけで差別化することが難しくなっています。その中で企業の差別化要因として「人材」の質がより重視されるようになりました。優れた人材がいるかどうかが新たな価値創出やイノベーションの源泉となるため、人材育成への投資が競争優位につながると考えられています。
深刻な人材不足と生産性向上の必要性
日本では少子高齢化に伴う労働力人口の減少により、慢性的な人材不足が大きな経営課題となっています。
リクルートワークス研究所の「未来予測2040」によると2030年には341万人あまり、2040年には1100万人あまりの労働供給不足が予測されております。
さらにIT分野に限ってみても、経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」では、IT需要の進み具合を一番低く見積もった場合でも2030年までに16.4 万人。IT需要の拡大具合が最大の場合で約78.7 万人の人材不足になると推計されています。
このように人材獲得競争が激化する中、今いる社員一人ひとりのスキル向上と生産性向上が不可欠です。限られた人員で高い成果を出すためにも、人材育成による戦力強化が求められています。
詳しくは「業界ごとに見る人手不足:理由と今後の対策をランキング付きで解説」の記事をご覧ください。
雇用の流動化と定着率向上
終身雇用が当たり前ではなくなり、人材が流動化する時代においては、社員に成長の機会を提供し続けることが定着率向上に直結します。
特に若手層は「有意味でやりがいのある仕事」を求める傾向が強く、成長実感が得られれば働きがい(エンゲージメント)が高まり、優秀な人材の離職防止にも効果があります。逆に言えば、成長の機会を提供できない企業からは人材が流出してしまう可能性が高まります。
「就職白書2024 」によると、若者の早期離職の理由が、キャリアの早期構築願望に基づくものであると報告されています。
「早くどこでも活躍できる人材になりたい」という意識が高まっているため、「この企業にいたら、将来のキャリアの見通しが持てない」と感じたら早めに見切りをつける傾向にあるということです。
企業戦略との連動
人材育成は単なる社員教育ではなく、経営戦略を達成する手段として位置づけられるようになりました。1980年代以降、「人材は重要な経営資源」との認識が広がり、人材育成にも経営目標に沿った明確な目的が求められるようになっています。
例えば新規事業に必要なスキルを育てる、グローバル展開に備えて語学や多文化対応力を高める、といった具合に、企業の将来ビジョンに沿った育成が重視されています。

人材育成の最新トレンド
次に、人材育成を取り巻く最新のトレンドを見てみましょう。社会や技術の変化に伴い、育成手法や考え方も進化しています。
リスキリング(Re-skilling)
リスキリングとは
「新しい職務に就くため、または現在の職務に必要なスキルの大幅な変化に対応するために、必要なスキルを新たに習得させること」
を指し、近年人材育成のキーワードとなっています。
DX時代の急激な環境変化に対応するには、従来の延長で学べない全く新しいスキルを身につける必要があり、各社でリスキリング推進の動きが盛んです。特にデジタル技術の台頭により、AIやデータ分析など未経験分野のスキル習得を社員に促すケースが増えています。
職場外研修(Off-JT)からオンライン研修へ
以前はOff-JT(職場外研修)といえば集合研修が主流でしたが、オンライン研修やeラーニングの普及が著しいです。
新型コロナウイルス禍を契機にWeb会議システム等を使ったオンライン研修が一般化し、地理的制約なく研修を実施できるようになりました。これにより、遠隔地の社員も同等の研修機会を得られたり、研修コストの削減が図られたりしています。
一方でオンライン研修では双方向性や実践性をどう担保するかが課題となり、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド研修や、eラーニング上での演習・テストを織り交ぜる工夫が進んでいます。
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)偏重から計画的育成へ
日本企業では伝統的にOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング:現場での実地指導)に頼る傾向が強く、かつては「現場で教えていれば人は育つ」と考えられていました。
しかし近年は現場の育成力の低下や指導できる管理職の不足も指摘されており、場当たり的なOJTだけでは不十分です。
体系的・計画的な育成へのシフトが見られます。
厚生労働省「令和5年度 能力開発基本調査 調査結果の概要」によると、正社員に計画的OJTとOff-JTを実施している企業はそれぞれ6~7割程度ですが、約8割の企業が「OJT重視」だと回答しつつも研修(Off-JT)も併用するバランスが重要だと認識しています。
現場経験(OJT)70%、上司や先輩からの指導20%、研修や自己学習10%という「70:20:10の法則」(ロミンガーの法則)も知られており、複数の手法を組み合わせて人材を育てる考え方が一般化しています。

人材育成に関する企業課題の顕在化
人材育成の必要性は理解しつつも、多くの企業が以下のような課題に直面しています。
・指導する人材(トレーナー)の不足
・日常業務が忙しく育成の時間が取れない
・育成してもせっかく育てた人材が離職してしまう
・効果的な育成方法が分からない・体系化できていない
・管理職の中に「教育してもどうせ成果は上がらない」と消極的な者がいる
・技術革新のスピードに対し、教える側の知識が古くなっている
これらの課題は、逆に言えば正しい知識と戦略で人材育成に取り組めば解決できるものが多いとされています。
次世代リーダー育成への関心
将来の企業を担うリーダー人材の育成は喫緊の課題で、多くの企業が人材育成を経営課題として捉えています。
以上のように、技術革新・市場環境・労働市場の変化など複合的な要因から、人材育成は企業経営の最重要テーマの一つとなっています。
主な人材育成手法とその特徴
人材育成の手法には様々なものがありますが、一般的にOJT、Off-JT、自己啓発の3つが代表的と言われます。さらに近年はメンター制度や1on1ミーティング、eラーニングなども活用されるようになっています。それぞれのメリット・デメリットを押さえ、組み合わせて活用することが効果を高めるポイントです。
OJT(On-the-Job Training) – 職場内教育
上司や先輩社員がトレーナーとなり、日常業務を通じて指導・訓練する方法です。現場の実業務をこなしながら技能やノウハウを身につけることで、即戦力化しやすい利点があります。例えば接客や営業、製造現場でのスキル習得にはOJTが適しています。
また、指導者とのコミュニケーションを通じて企業の風土や文化も学べるという効果もあります。一方で、指導内容が属人的になりやすいという課題があります。
教える先輩のスキルや経験に左右されてしまい、指導の質にばらつきが出たり、体系立てた教育になりにくい傾向があります。そのため、企業側でOJTトレーナーの育成研修を実施したり、指導マニュアルを用意するなどして、OJTの質を担保するフォローが必要です。
適任者の選出とトレーナーへの支援がOJT成功のカギとなります。
Off-JT(Off-the-Job Training) – 職場外研修
通常の業務を離れて行う研修全般を指します。新人研修、管理職研修、専門スキル研修など、計画的・体系的に知識やスキルを習得させるのに適した方法です。
社内講師による研修のほか、研修会社主催のセミナーに派遣したり、講師を招いて社内研修を実施するケースも一般的です。
メリットは、体系立てて幅広い知識を学べることと、指導者の力量に左右されにくい点です。最新の専門知識や他社事例を学ぶ機会にもなり、視野を広げる効果もあります。近年はオンライン研修も増え、地理的制約なく多拠点の社員に一斉研修を実施することも容易になっています 。
デメリットとしては、現場の実情とかけ離れた内容になってしまうと実務に活かされにくいこと、研修の準備や費用がかかることなどがあります。研修で学んだ知識を現場でどう定着させるか(研修後のフォロー)が重要です。
また、業務を離れる時間の確保が難しい場合は短時間のオンライン講座や現場内勉強会など工夫してOff-JT機会を作る企業もあります。

自己啓発(Self Development) – 自発的学習
社員が自らの意思でスキル向上や知識習得に取り組むものです。具体的には、業務時間外に資格取得の勉強をしたり、オンライン講座を受講したりといった活動が該当します。
自己啓発は本人の意欲に基づくため高い効果が期待できますが、強制してしまうと自主性が失われモチベーションが下がる恐れがあり、あくまで社員の自主性尊重が前提です。
日本企業では従来、OJTと本人の自己啓発に委ねる部分が大きかったため、企業によっては自己啓発支援制度を設けて社員をバックアップしています。例えば資格取得費用の補助や報奨金、通信教育の受講補助、社外研修への派遣など、学ぶ意欲のある社員を会社が経済的・制度的に支援する仕組みです。
このような後押しにより社員の学習意欲を引き出し、自己研鑽の風土を醸成している企業も増えています。
一方で、実際には忙しさなどから勤務先以外で自己研鑽を行っていない社会人が約半数にのぼるという調査結果もあります。
そのため、業務と学習の両立を支援するために、勤務時間内に学習する時間を認めたり、副業制度を通じて社外で経験を積む機会を与えるなど、新しい取り組みを始める企業も出てきています。
メンター制度・コーチング・1on1ミーティング – 対話型の育成支援
近年注目されるのが、上司や先輩とは別にメンター(相談役)を新人社員につける制度や、上司と部下が定期的にじっくり対話する1on1ミーティングです。
メンター制度は、新人が悩みやキャリアについて気軽に相談できる年次の離れた先輩社員をマッチングするもので、業務指導とは一線を画したメンタル面のサポートや助言が期待できます。
また、コーチング研修を受けた上司が部下に対し質問や傾聴を通じて自発的な気づきを促すコーチング手法もリーダー層の必須スキルになりつつあります。定期的な1on1では業務上の課題だけでなくキャリア目標や成長実感について話し合い、上司が部下の成長を継続的に支援・伴走します。
これら対話型の手法は、社員の心理的安全性を高め意欲を引き出す効果があり、離職防止にも有効だとして多くの企業で導入が進んでいます。

その他の手法
以下のような手法があります。
アクションラーニング(実課題に取り組むプロジェクト型研修)
ジョブローテーション(異なる部署や職種を経験させ視野と技能を広げる)
社内公募制度(新規事業や他部門のポストに社内から挑戦応募できる制度)
外部セミナーや大学院への派遣(社外の教育機関で専門知識を習得)
企業規模や業種によって最適な手法は異なりますが、大切なのは一つに偏らず複数の方法を組み合わせることです。
現場経験と集合研修、自主的な学びをバランス良く繰り返すことが人材育成成功の近道だとされています。
効果的な研修プログラムの設計と実施のポイント
効果的な研修プログラムを実施するには、体系立てた計画(プラン)に基づき、実行・評価・改善することが重要です。
研修企画から実施、フォローアップまでのポイントをまとめます。
経営方針・育成理念の共有
まず会社として人材育成にどう取り組むか、全社的な思想や理念を明確にし共有しましょう。
「人材は最大の資産」「学習し続ける組織を目指す」など、経営トップからのメッセージ発信により、社員の意識を高めることが土台となります。
経営層が人材育成にコミットし支援する姿勢を示すことで、現場も安心して育成に時間と労力を割けるようになります。
人材育成ニーズの把握(現状分析)
次に、自社の人材育成ニーズを洗い出します。
自社が抱える課題(例:リーダー層のマネジメント力不足、デジタル人材の欠如など)や、今後必要となるスキルを整理します。
360度評価や社員アンケート、業績評価結果などを分析し、「誰に・何を身につけさせるべきか」を明確にします。職種別・階層別に求められる能力を定義したコンピテンシーモデルや、前述のスキルマップを活用すると、育成すべきスキルギャップが可視化され計画に落とし込みやすくなります。

育成目標と方針の策定
分析結果を踏まえ、育成の目的・目標を設定します。「新人営業の早期戦力化」「次期リーダー候補の育成」「全社員のITリテラシー向上」など、具体的な目標を掲げましょう。
あわせて、人材育成方針を策定します。ポイントは経営戦略と紐づけることです。
例えば「3年後の海外展開に向け全営業の英語力〇〇レベル達成」など、事業計画と連動した育成目標を立てます。
その際、達成指標(KPI)も設定できるとなお良いでしょう。
育成方針は人事部門だけで決めるのではなく、経営層と各現場管理職ともコンセンサスを取りながら策定することが重要です。
現場の協力なくして育成施策は絵空事になりかねないため、関係者を巻き込んで方針を練り上げます。
研修計画の立案(プランニング)
育成方針に基づき、具体的な研修プログラムを設計します。対象者、内容、期間、頻度、手法(OJT/Off-JT/自己啓発等)、担当講師、必要予算などを決めていきます。
各層・職種ごとの教育体系図を作成し、社員がキャリアに応じてどんな研修を受けるかロードマップを示すのも有効です。
年間計画として新人研修→フォロー研修、管理職研修、専門スキル研修、全社講演会…とカレンダーに落とし込みます。
社内資源で賄えない分野は外部研修や通信教育の活用も検討します。また、研修計画には評価方法(研修後テストやアンケート、現場上長からのフィードバックなど)も組み込んでおきます。
研修の実施(Do)
計画に沿って研修を実施します。研修実施段階で留意すべき点として、参加者の主体的参加を促す工夫があります。大人数の講義形式だけでは受け身になりがちなので、ディスカッションやワークショップ形式を取り入れたり、現場で課題を持ち帰ってもらい実践させる仕掛けを用意すると効果的です。
また、OJT担当者には事前に研修の目的や教えるポイントを共有し、質のばらつきを減らします。Off-JTでは研修後に上司に対して学んだ内容の報告を義務づけるなど、現場との接点を作ると定着しやすくなります。
研修中は受講者の反応を観察し、柔軟に進め方を調整することも大切です。
効果測定とフォローアップ(Check & Act)
研修は実施して終わりではありません。効果測定を行い、次につなげることが重要です。研修直後の受講者アンケートで満足度や理解度を測るのはもちろん、その後の業務での行動変容や業績向上につながったかを評価します。
具体的には、研修前後のKPI変化(例:研修受講者の生産性指標が○%向上)や、上司による研修後の部下評価、面談での成長実感のヒアリングなど、多面的に効果をチェックします。
また、研修で学んだ内容を現場で試してみるアクションプランの実行状況をフォローし、困りごとがあれば追加指導や補講を行います。評価のフレームワークとして有名なカークパトリックの4段階評価モデル(反応・学習・行動・成果)なども参考になります。
評価結果を踏まえて研修内容や手法を改善し、PDCAサイクルを回して育成施策のブラッシュアップを続けましょう。
環境・風土づくり
プログラムの内実だけでなく、社員が成長し続けられる組織風土を醸成することも重要です。日頃から上司が部下のチャレンジを支援し、失敗を責めず学びに変える姿勢を示すことで、「学んで試す」ことを良しとする文化を根付かせます。
社内勉強会の奨励や、資格取得者の表彰、ナレッジ共有の仕組みづくり(社内Wikiや情報共有ツールの活用)なども有効でしょう。社員同士が教え合う文化ができれば、公式な研修だけでなく日常業務の中で人が育つ土壌ができます。

外部リソース・助成制度の活用
全てを自社だけで賄おうとせず、使える外部リソースは積極的に活用しましょう。例えば業界団体や公的機関が提供する研修プログラム、大学との連携講座、オンライン学習プラットフォーム(CourseraやUdemyなど)の活用などがあります。
また、日本には厚生労働省の「人材開発支援助成金」のように、計画的な人材育成を行う企業に対して研修経費や講師謝礼、受講中の賃金の一部を支給する助成制度があります。
特定の要件(若手向け訓練やOJT+Off-JT併用の研修など)を満たすと助成額が高く設定されており、これら制度を上手に活用すれば人材育成のコスト負担を大幅に軽減できます。
申請には研修計画の作成やジョブカードの発行等が必要ですが、該当コースに沿って研修設計を行うことで大きなメリットが得られます。このように公的支援も視野に入れ、費用面のハードルを下げて計画的な育成を推進しましょう。
以上が効果的な研修プログラム設計・実施の大まかな流れとポイントです。
要は、「戦略に基づく計画」→「適切な手法の組合せで実行」→「効果検証と改善」を回すことで、人材育成施策の質を高めていくことができます。次章では、特にニーズの高いリーダーシップ開発と、企業の人材マネジメント上のポイントについて掘り下げます。
リーダーシップ開発のポイント
次世代のリーダーをどう育てるかは、多くの企業が直面するテーマです。リーダーシップ開発では、将来の管理職や経営幹部候補となる人材に対し、早期かつ計画的な育成機会を提供する必要があります。具体的なポイントをいくつか挙げます。
ハイポテンシャル人材の選抜と育成計画
まず、リーダー候補となりうるハイポテンシャル人材(高い潜在能力を持つ人材)を早期に見極めることが重要です。
入社年次に関係なく、仕事への取り組み姿勢や影響力、学習能力などを評価し、将来有望な人材を選抜します。
その上で、彼らに対して個別の育成計画(IDP: Individual Development Plan)を策定します。具体的な目標ポジションや習得すべきスキルを定め、計画的にキャリアを積ませるのです。

ストレッチアサイン(高チャレンジな任務付与)
リーダーシップは机上では身につかず、実践を通じて育まれる側面が大きいものです。新人時代から責任ある仕事を「任せて伸ばす」ことが効果的です。意欲ある社員には年次相応以上のプロジェクトリーダーや新規企画などストレッチ目標を与え、試行錯誤させることでリーダーシップを発揮する機会を提供します。
困難な経験を積むことで、課題解決力やチームマネジメント力、意思決定力などリーダーに必要な資質が鍛えられます。
ただし、任せっぱなしではなく、必要に応じて上司やメンターがサポートし、失敗から学べるフォロー体制も用意しておきましょう。
リーダーシップ研修・トレーニング
実務経験に加えて、体系的なリーダーシップ研修も有効です。たとえば、「新任管理職研修」「次世代リーダープログラム」などの名称で、マネジメントの基礎やリーダーに求められるスキルを学ぶ場を設けます。
内容としては、コーチングや部下育成の手法、目標管理のやり方、財務知識、戦略思考、コンプライアンス、人間力(コミュニケーション・傾聴・意思疎通)など多岐にわたります。
またアセスメントセンター方式で模擬的な管理職業務を体験させフィードバックする研修も効果があります。研修で得た知識をすぐ現場で試せるように、実務と研修を往復させながら習得度を高めます。
メンタリングとロールモデル
次世代リーダーには、身近にロールモデル(模範となる先輩像)を示し、メンターとして伴走してもらうことも有効です。
例えば部長クラスの幹部が若手リーダー候補数名のメンターとなり、定期的にキャリア面談や助言を行う制度を作ります。先輩リーダーから直接学ぶことで暗黙知が伝承され、またネットワークづくりにもなります。
メンターは成功体験だけでなく自身の失敗談も共有し、若手が壁にぶつかった際に適切に支援します。社内にロールモデルとなるリーダーが少ない場合は、外部の経営者講話や異業種交流の機会を提供し、視野を広げさせるのも一つです。
360度フィードバックと自己認識
リーダー層の育成には、自身の強み・弱みを客観的に知る機会も大切です。360度評価(多面評価)を用いて、上司・同僚・部下といった複数の視点からフィードバックを受けると、自ら気付かなかった改善点が見えてきます。
これをもとに個々のリーダー候補が自己成長目標を立て、コーチや上司の支援のもと能力開発に取り組むという方法も効果的です。自己認識を深め、理想のリーダー像とのギャップを埋めていくプロセスを経ることで、人間的な成長が促されます。
継続的なリーダーシップ経験
一度管理職になって終わりではなく、その先も継続的に学び続ける仕組みが必要です。
例えば管理職研修を階層ごとにシリーズ化し、課長昇格時、次に部長昇格時、その後も数年おきにフォロー研修を行うなど、生涯にわたってリーダーシップをアップデートする場を用意します。
社外の経営塾やビジネススクールに派遣することも有効でしょう。
常に新しい知見を取り入れ、時代に合ったリーダーシップを発揮できるよう研鑽する文化をリーダー層に醸成します。

人材マネジメント上のポイント
次に、企業全体の人材マネジメントの観点から、人材育成と密接に関わるポイントを押さえておきましょう。人材マネジメントとは、採用・配置・評価・育成・定着といった人事の一連の流れを戦略的に運用することですが、ここでは特に育成と関連の深い事項を取り上げます。
人事評価と育成の連動
人材育成を効果的に進めるには、人事評価制度と育成施策を連動させることが重要です。評価面談の場で上司が部下の強み・弱みをフィードバックし、次期の成長目標を話し合うようにします。
評価項目に「自己研鑽の取り組み」や「部下育成の実践」を含め、育成に力を入れた社員・管理職がきちんと評価される仕組みにすることも有効です。
例えば部下を〇名昇進させたマネージャーを高評価にする、資格取得者には加点する、といった形で育成行動をインセンティブ化します。
評価と育成を切り離さず、サイクルの中で回すことで、社員はフィードバックを元に成長し、上司は部下育成を自らの責務と認識するようになります。
キャリアパスの明示と支援
社員が長期的視点で成長していけるよう、キャリアパスを複数用意して明示することも大切です。管理職だけでなく専門職コースを設けるなど、社員が自分の志向に合った道で力を伸ばせるようにします。
さらに社内公募や社内FA制度で部署異動の機会を提供したり、希望するキャリアに必要な研修への参加を支援したりします。社員一人ひとりが「将来こうなりたい」というビジョンを持ち、それに向けて会社が伴走する形が理想です。
定期的なキャリア面談を人事部や上司が行い、キャリア形成を後押ししましょう。キャリア開発支援が充実している会社は社員のエンゲージメントも高まり、結果として自主的な学習意欲も高まります。

人材データの活用(タレントマネジメントシステム)
最近では、社員のスキル・経験・志向性などのデータを一元管理するタレントマネジメントシステムを導入する企業も増えています。これを活用すると、全社の人的資源状況を見える化でき、適材適所の配置や育成計画の精度が向上します。
例えば、誰がどの研修を受講済みか、どの資格を保有しているか、評価履歴や自己申告情報などをデータベース化しておけば、プロジェクトに最適な人選や後継者計画の策定に役立ちます。
さらに、人材データを分析して「離職リスクの高い人材に早めに手を打つ」「特定スキル保有者が不足する部署に重点育成する」といった戦略的人材配置・育成が可能になります。
ただしシステムはあくまで手段なので、活用の前提として現場と人事が密に連携し、日頃から情報共有・コミュニケーションを図ることが重要です。
従業員エンゲージメントの向上
人材マネジメントでは、社員のエンゲージメント(会社への愛着やコミットメント)を高めることも重視されます。前述の通り、人材育成はエンゲージメント向上と離職防止に直結します。
社員が成長実感を得られれば会社への貢献意欲も増し、定着にもつながります。そのため、育成施策を打つ際には社員の声に耳を傾け、ニーズを的確に捉えることが重要です。
「こんな研修を受けたい」「ここが不安だ」といった意見をアンケートや1on1で吸い上げ、施策に反映しましょう。
また、頑張ってスキルアップした社員を称賛・表彰するなど承認欲求を満たす仕掛けも有効です。
エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)で育成施策の満足度や会社への誇り度合いを測定し、PDCAを回す企業も増えています。
多様な人材の活躍推進
人材マネジメントでは、多様性の尊重と活躍推進も重要テーマです。女性管理職の登用、シニア層の活用、外国籍人材の受け入れなど、人材のバックグラウンドが多様になる中、それぞれの強みを活かす育成が求められます。
例えば女性リーダー育成研修や、シニア社員の再教育プログラム、外国人社員向け研修・日本語教育など、対象に応じた施策を展開します。
また、多様な人材がお互い学び合えるクロスカルチャー研修やチームビルディングも有効です。多様性を活かす風土づくりと人材育成を両輪で進め、組織全体の力を底上げします。
以上、リーダーシップ開発と人材マネジメントの観点から重要なポイントを述べました。
未来のリーダーを見据えた育成と、公平かつ戦略的な人材マネジメントが、企業の持続的成長には欠かせません。

デジタルスキル・DX対応人材の育成
現代の企業にとって、デジタル技術への対応力を持つ人材、いわゆるDX人材(デジタルトランスフォーメーションを推進できる人材)の育成は急務となっています。
AI・IoT・ビッグデータなど先端技術の活用がビジネスの成否を分ける中、それを扱える人材が不足しているためです。ここではデジタルスキルとは何かから始め、DX人材を育てるための施策について解説します。
DX人材とは何かとその不足状況
DX人材とは、一言で言えばデジタル技術を活用してビジネスに新たな価値を生み出せる人材を指します 。具体的には、データ分析やAI開発ができる高度IT人材だけでなく、自社の業務にITを取り入れて効率化・革新を起こせる人材、デジタルプロジェクトをリードできる企画人材など幅広い層を含みます。
近年はほとんどの業種でDXが叫ばれていますが、日本企業ではこのDX人材が圧倒的に不足しています。経済産業省による「デジタル人材育成プラットフォーム の取組状況について」では、日本企業の76%がDX人材の不足を感じているという超さ結果も出ています。
ちなみに米国では同様の回答は43%に留まるとのことのことですので遅れを取っていると言えるでしょう。
多くの企業にとって、既存社員をDX人材へ育成する(リスキリングする)ことは避けて通れない課題と言えるでしょう。
DX推進については「DX推進とは?:採用を切り口とした7つのメリットと成功のコツ」の記事で詳しく解説しました。
デジタルスキルの種類
一口にデジタルスキルと言っても、その内容はレベルによって様々です。企業内で育成すべきデジタルスキルを整理すると概ね次のようになります。
基礎的デジタルリテラシー
全社員に求められる水準。Officeソフトやチャットツールの活用、ビジネスデータの基本的な取り扱い、リモート会議ツールの利用法、情報セキュリティの基礎知識など。「当たり前」のITスキルですが、高年齢層など苦手な社員もいるため教育が必要。
業務効率化スキル
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールの利用や、Excelマクロ・簡易なプログラミングによる業務自動化、業務アプリケーション(ERPやCRM等)の活用スキルなど、各部門の業務DXに直結するスキル。これらは現場部門の社員にも身につけさせることで、生産性向上が期待できます。
データ活用スキル
データ分析・活用に関わるスキル。ビジネスデータを集計・可視化するBIツールの使い方、統計分析手法の基礎、マーケティングデータの解析、場合によってはPythonやSQLなどを用いたプログラミングによるデータ抽出・分析まで含みます。
今や多くの部門でデータドリブンな意思決定が求められるため、データリテラシー研修を全社員向けに実施する企業もあります。
高度ITスキル
システム開発やAI実装、クラウドインフラ構築など専門的スキル。従来は情報システム部やIT子会社のエンジニアだけの領域でしたが、事業部門でもプロジェクトマネージャーがこうした知識を理解している必要が出てきています。
社内にIT人材が不足している場合、既存社員をエンジニアにリスキリングする取り組みもありえます。
特にエンジニアは獲得競争が激しく、採用もなかなか難しくなってきました。既存のメンバーのリスキリングの重要性は高まっています。
とはいえ、いざという場面では経験のあるエンジニアが必要なケースも多々あるのが現実です。「エンジニア採用が難しい理由」のなかでは、エンジニア採用が難しいくなった背景と採用に向けてどのような取り組みができるのか、といった点を扱いました。
DX推進スキル
DXプロジェクトを企画立案・推進するスキル。ビジネスとITの橋渡し役となり、業務プロセスの変革をリードできる能力です。具体的には、デザイン思考やアジャイル開発の知識、プロジェクトマネジメント、社内説得・チェンジマネジメント力、外部パートナーとの協業スキルなどが該当します。
これらは単一の研修で身につくものではなく、経験と研修を組み合わせて養成していく領域です。
DX人材を育成するための施策
では、こうしたデジタルスキルを社員に身につけてもらうにはどうすればよいでしょうか。いくつか有効な施策を紹介します。
社内デジタル研修の体系化
まず、社内でデジタル研修体系を整備しましょう。
例えば、新入社員研修で全員に基礎IT研修を行い、中堅層には業務で使えるエクセルマクロやRPA研修、管理職層にはデータ活用やDX戦略研修、といったように階層別にカリキュラムを組みます。IT部門の専門家や外部講師を招いて定期的に講座を開催するのも良いでしょう。
またeラーニングも積極活用します。社内ポータルにデジタルスキルの動画教材を用意し、社員が自主学習できる環境を提供します。
デジタル人材育成プログラム(選抜制)
全社員対象とは別に、将来的にDXを牽引してもらうデジタル人材育成プログラムを作る企業もあります。
公募や推薦で選抜した社員を一定期間集中的に育成するものです。内容は、外部のデジタル人材育成講座への派遣や、実際のDXプロジェクト参画、ハッカソンへの参加、社長直轄の課題解決チームへの抜擢など多様です。
選抜制にすることで本人のモチベーションも上がり、修了後はDX推進のコア人材として活躍してもらいます。

リスキリング支援(社外スクール活用等)
未経験の分野を学ぶには専門の教育機関を利用するのも手です。近年プログラミングスクールやデータサイエンス講座が充実しているので、社員を一定期間(例: 3ヶ月間のブートキャンプ型研修)送り込むケースもあります。
経済産業省も社会人のリスキリングを支援する施策を拡充しており、補助金を活用して社外研修に参加させることも可能です。社内に講師がいない領域は、思い切って社外のプロに任せることで効率的に育成できます。
現場での実践機会提供
やはり実務を通じた学習が欠かせません。例えば、自社の業務課題に対してRPAツール導入プロジェクトをチームで行わせる、データ分析PJを立ち上げて若手に主導させる、などミニDXプロジェクトを現場に仕掛けます。
経験豊富なITベンダーと組み、プロジェクトを動かしながら社員が実践から学ぶ「オンザジョブDX研修」のイメージです。できれば失敗しても大きな影響が出にくい小規模案件から始め、成功体験を積ませましょう。現場で成果が出れば本人の自信にもなり、周囲にもDX推進の機運が高まります。
社内専門家の育成と配置
社員の中からデジタルの専門家(内製人材)を育てることも長期的には重要です。
例えばIT部門の若手を重点的に育成し、AIやクラウドの資格取得を支援してスペシャリストにする、事業部門にもテックリード役を置いて部門のIT化をリードさせる、といった取り組みです。
専門家が社内にいると教育の内製化も進みますし、日常業務での相談役にもなってもらえます。
複数人のデジタル人材が横串でつながるコミュニティ(社内勉強会やSlackグループ等)を作り、情報交換やナレッジ共有する場を設けるのも有効です。
最新技術への対応
DX人材育成では、常に最新の技術トレンドを意識する必要があります。例えば近年話題の生成AIについて、社内で勉強会を開いたり試験導入してみる、IoT機器の使い方を実習してみるなど、アンテナを高く保ちましょう。
社員が新しい技術に触れる機会を与え、「まずはやってみる」文化を育むことが、DX推進には欠かせません。
外部採用との組み合わせ
ここまで主に社内育成の視点で述べましたが、即戦力のDX人材を中途採用することももちろん有効な手段です。中途入社のデジタル人材と、既存社員の業務知識豊富な人材が協働することで相乗効果が生まれます。
ただし、外部人材にばかり頼るのではなく、社内人材も育てるという姿勢が長期的には重要です。外部から来たプロフェッショナルに社内勉強会で講師をしてもらい、ナレッジ移転を図るのも良いでしょう。
このように、多角的なアプローチで社員のデジタルスキルを底上げしていくことが肝要です。特に基礎的なITリテラシーは全社員に不可欠ですし、DXを牽引する中核人材も育てなければなりません。国全体としてもデジタル人材育成は重要課題であり、各企業の取り組みが業界全体の国際競争力にも影響します。
DX人材育成に成功した企業は、市場環境の変化に柔軟に適応できる強みを持つことになるでしょう。

人材育成の今後
最後に、人材育成の今後の展望と、企業が今から取るべき具体的なアクションプランについてまとめます。時代の流れを捉えた戦略的な人材育成に乗り出すことで、自社の未来を切り拓いていきましょう。
継続学習(ラーニングアジリティ)の重要性
テクノロジーの進歩や市場変化のスピードが増す中、一度身につけたスキルが陳腐化するまでの期間が短くなっています。そのため、社員が継続的に学び続けること(ラーニングアジリティ)がこれまで以上に重要になります。
企業としても、一回限りの研修で満足するのではなく、社員がキャリアを通じて学び続けられる仕組みを整える必要があります。例えば社内大学の設立や、自己啓発費用補助の恒久的制度化、学習成果を社内で共有する文化づくりなど、生涯学習を支える企業文化が展望されます。
人材育成×テクノロジー(HRテック)の活用
人材育成自体にもテクノロジーが活用されていくでしょう。AIを活用したラーニングマネジメントシステム(LMS)は、各社員の習熟度データを分析し、一人ひとりに最適な学習コンテンツをレコメンドすることが可能です。
またVR(仮想現実)による危険作業の模擬体験研修や、ゲーミフィケーションを取り入れた楽しく続けられる eラーニングなど、研修手法そのもののイノベーションも進むでしょう。
チャットボットが新人の質問に24時間答えてくれる「AIメンター」のような存在も現れるかもしれません。これらHRテックを積極的に取り入れる企業が、効率的で魅力的な育成を実現していくと考えられます。
組織開発との融合
個人の能力開発だけでなく、組織として学習する組織(ラーニングオーガニゼーション)への進化が求められます。
人材育成と組織開発(OD: Organization Development)の境界が曖昧になり、研修で得た学びを組織全体で共有・実践するサイクルが重視されます。
具体的には、研修をチーム単位で受けてそのまま職場の業務改善に取り組む、上司と部下がセットで学ぶ、全社横断プロジェクトで新しいカルチャーを醸成する、といった動きです。
企業内に「学習する文化」が根付けば、環境変化にも適応しやすくなり、集団としての知的生産性が飛躍的に向上するでしょう。
多様化するキャリアと人材育成
副業・兼業の広がりや、転職が当たり前になる流れの中で、企業内だけで完結しない人材育成も増えると考えられます。社員が副業先で得たスキルを本業に活かすケースや、逆に社外のプロ人材がプロジェクト単位で社内に参画し社員が刺激を受けるケースも増えるでしょう。
人材の流動性が高まるからこそ、一社でのキャリアに縛られず「どこでも通用する人材」に育てるくらいの気概が求められます。その方が結果的に社員から選ばれる企業になり、優秀な人が集まり定着する好循環が生まれます。
エンゲージメント経営
人材育成は、従業員エンゲージメントの向上や企業理念の浸透と不可分になっていくでしょう。
社員が企業のビジョンに共感し、自身の成長と会社の成長を重ね合わせて捉えられるようなエンゲージメント経営が重要です。
そのために、人材育成の施策と企業の使命・価値観をしっかり紐づけ、「この研修は会社の〇〇戦略の一環であり、自分たちの成長が会社の発展につながる」という納得感を与えることが大切です。

企業が取るべきアクション
以上の展望を踏まえ、企業が今後ますます人材育成に力を入れていくために、具体的に取るべきアクションをチェックリスト的に挙げます。
経営戦略と人材戦略の統合
まず経営計画の中に人材育成の視点を織り込みましょう。3年後、5年後の事業ビジョン達成のために「どんな人材像が何人必要か」「社内のどの層をどう育てるか」を明文化します。
人材ポートフォリオを描き、育成投資計画を立て、経営会議で進捗をモニタリングするなど、経営課題として位置づけます。
人材育成の専任体制づくり
人事部内に人材開発専門のチームを設けるか、あるいは現場から人材育成担当をアサインしてタスクフォースを組織します。社内にノウハウがない場合は、研修会社や人材コンサルタントの力を借りるのも一つです。大事なのは「育成施策を企画運営し、PDCAを回す専任者」を置くことです。
育成ニーズの定期的な把握
社員や管理職へのヒアリング、アンケート、スキル診断を通じて、育成ニーズを定期的に洗い出します。
特に毎年のように技術が変わるIT領域などは年次ごとにニーズが変わるため、年度ごとに育成計画を見直すぐらいの柔軟さが必要です。従業員満足度調査などで「研修機会に満足しているか」といった設問を設け、声なき声も拾い上げましょう。
重点施策の絞り込みと実行
課題は多岐にわたるかもしれませんが、全部に手を付けようとして中途半端になるより、優先度の高いテーマに絞って集中的に取り組むことが成功のポイントです。
例えば「今年度は若手営業の育成に注力する」「来年度は管理職研修を充実させる」などテーマを定め、リソースを重点投入します。
先述のように次世代リーダー育成は多くの企業で喫緊の課題ですし、DX人材育成も待ったなしでしょう。自社にとって最重要な育成テーマを見極め、プロジェクト化して推進します。
育成効果の見える化
経営陣に納得して継続投資してもらうためにも、人材育成の効果を可能な限り数値化・見える化しましょう。
定量面では研修受講者の業績指標変化、離職率低下、従業員エンゲージメントスコア向上、資格保有者数増加などが指標となり得ます。
定性面でも「育成施策により〇〇な社風に変わってきた」等のエピソードを収集し発信します。
人材育成と企業業績の因果関係は一概に測りづらい部分もありますが、少なくともKPIを設定し追跡することで、社内の意識改革につながります。
社内への発信と展開
人材育成を盛り上げるには社内広報も大事です。社内報や朝会で研修修了者のコメントを紹介したり、学んだことを部署内で発表してもらったりします。
「〇〇研修を受けたら業務でこう役立った」という成功体験を共有し、他の社員の刺激とします。また管理職には「育成はあなたの重要なミッション」と繰り返し伝え、人材育成が評価項目に入ることも周知徹底しましょう。
継続的な改善
人材育成に終わりはありません。一度計画を立てても、環境変化や人事制度変更などに応じて柔軟に見直しが必要です。小さく始めてPDCAを回し、改善を積み重ねるアプローチが現実的です。
例えば初めて実施した研修で期待した効果が出なければ内容や対象を変えて再実施する、受講率が低ければ受講しやすい工夫をする、といった具合にアジャイルに育成施策を改善していきましょう。
最後に強調したいのは、人材育成の最終目的は経営目標の達成であるということです。人を育てること自体が目的化してしまっては本末転倒であり、育成を通じて事業成果を出してこそ意味があります。しかし裏を返せば、社員の能力が最大限に引き出された組織は鬼に金棒です。
人材育成によって今いる人材一人ひとりのスキル向上を促し、生産性を向上させることで、企業の競争力強化につなげましょう。今日からぜひ、皆さんの会社でも人材育成の新たな一歩を踏み出してみてください。それが将来の大きな成果となって返ってくるはずです。

まとめ
人材育成は企業の競争力強化や持続的成長に不可欠であり、特にDX時代においてはデジタルスキルの習得が求められています。この記事では、企業の成功事例や研修プログラムの最新トレンドを紹介し、効果的な育成戦略のポイントを解説しました。
リーダーシップ開発やマネジメントの工夫、OJT・オンライン研修の活用など、多角的なアプローチが鍵となります。企業はこれらを踏まえ、戦略的に人材育成を進めることで、持続的な成長と競争力強化を実現できます。
・人材育成は企業成長の鍵
・研修プログラムは戦略的に設計・実施すべき
・DX時代に適応するスキル育成が重要
以上のポイントを押さえ、持続的な企業成長を実現するために、効果的な人材育成戦略を策定しましょう。
高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ
お客様も気づかなかったベストマッチを
人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。
会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。
そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。
「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて
また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。
でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。
圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで
ロケットスタートホールディングスは、IndeedシルバーパートナーとしてIndeed/Indeed PLUSを活用した採用成功への伴走支援を行っております。

※ IndeedシルバーパートナーはIndeedの定めた正規認定パートナーの証しです。
地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様に最適なプランを1社1社丁寧にご提案いたします。最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。