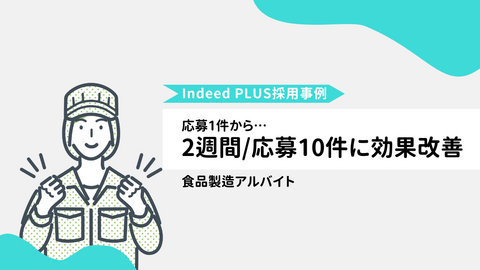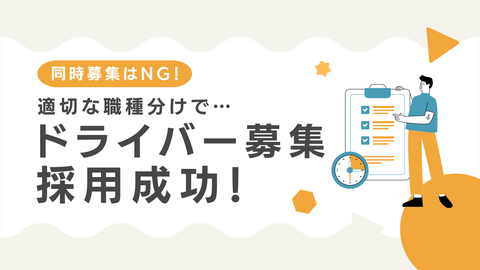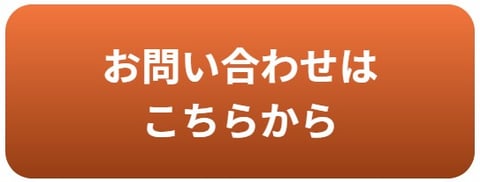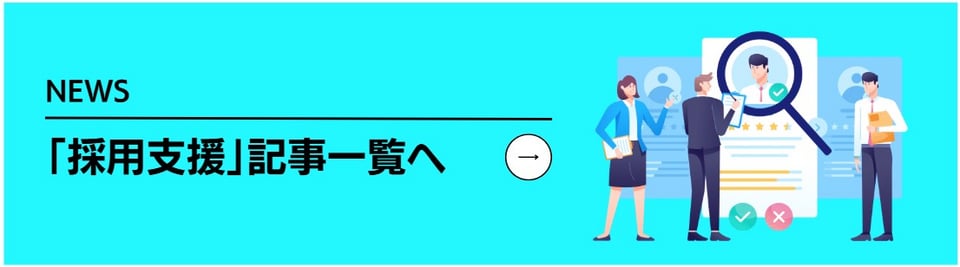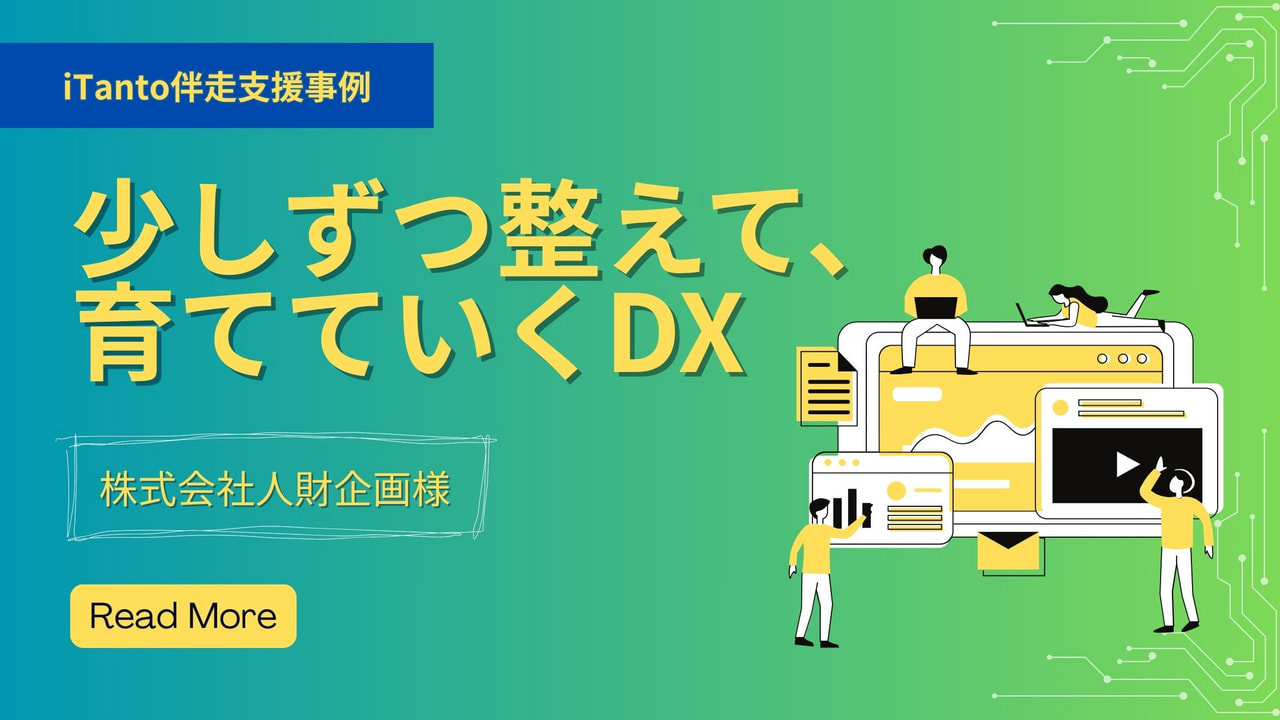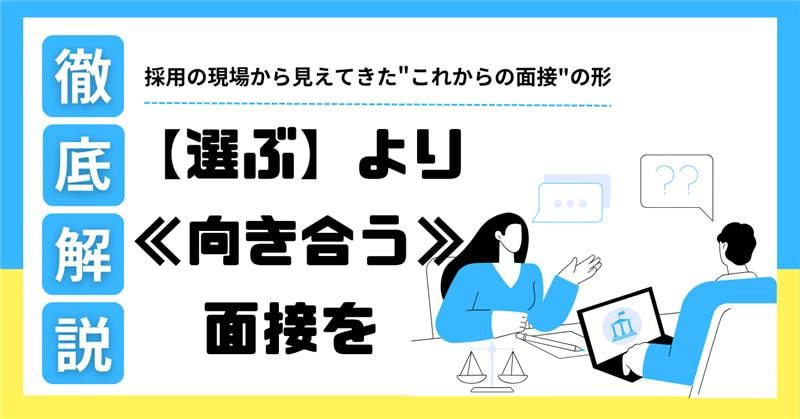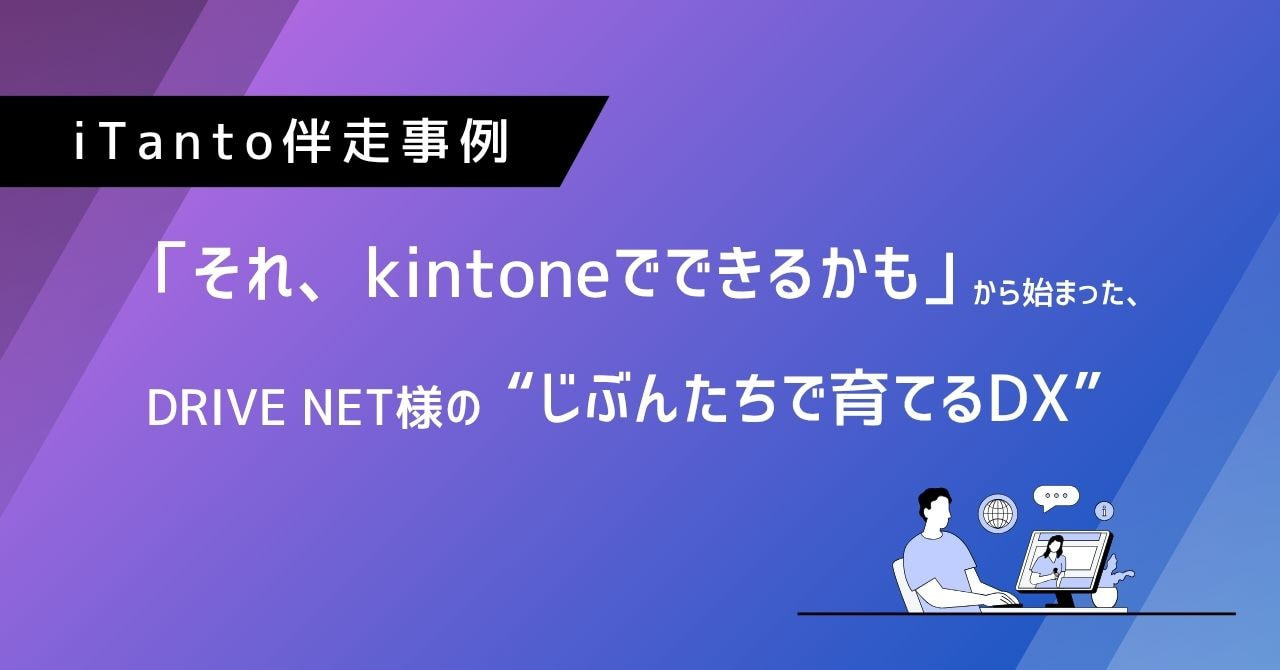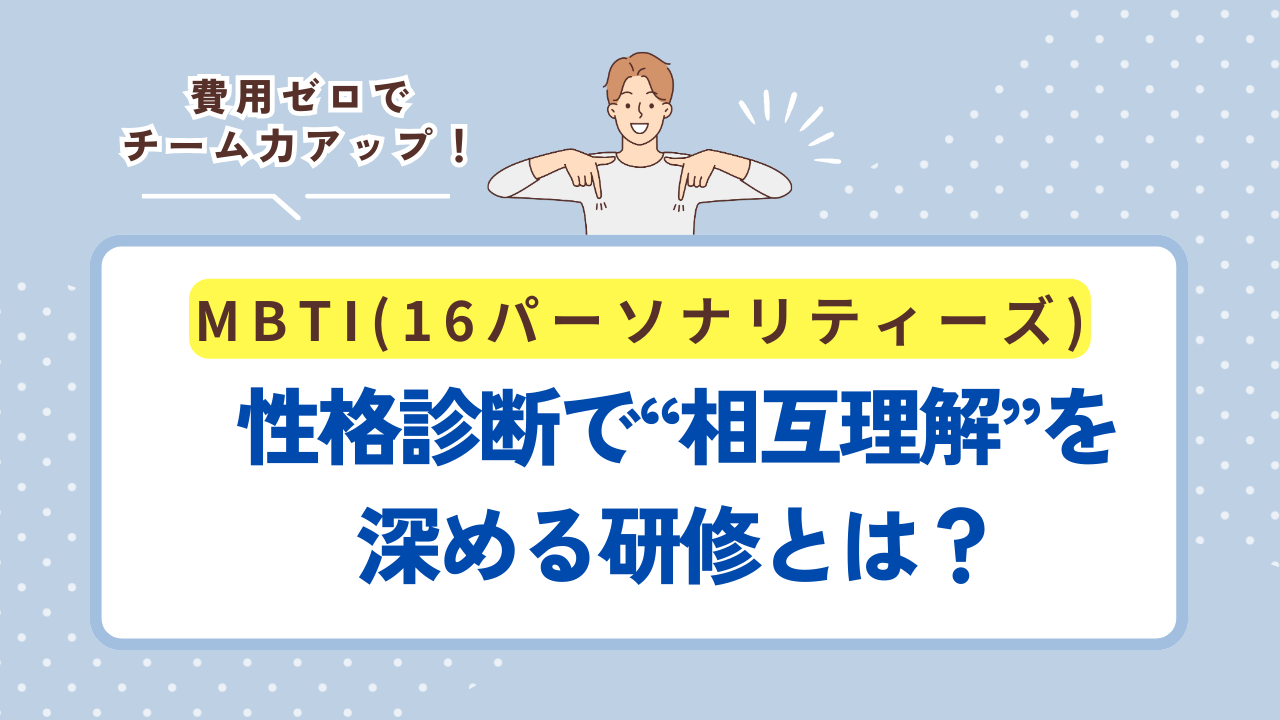公開日: 2024年09月30日 / 更新日: 2025年12月26日
ロケスタ通信採用支援
新卒・中途一人当たりの採用コスト:相場と削減方法
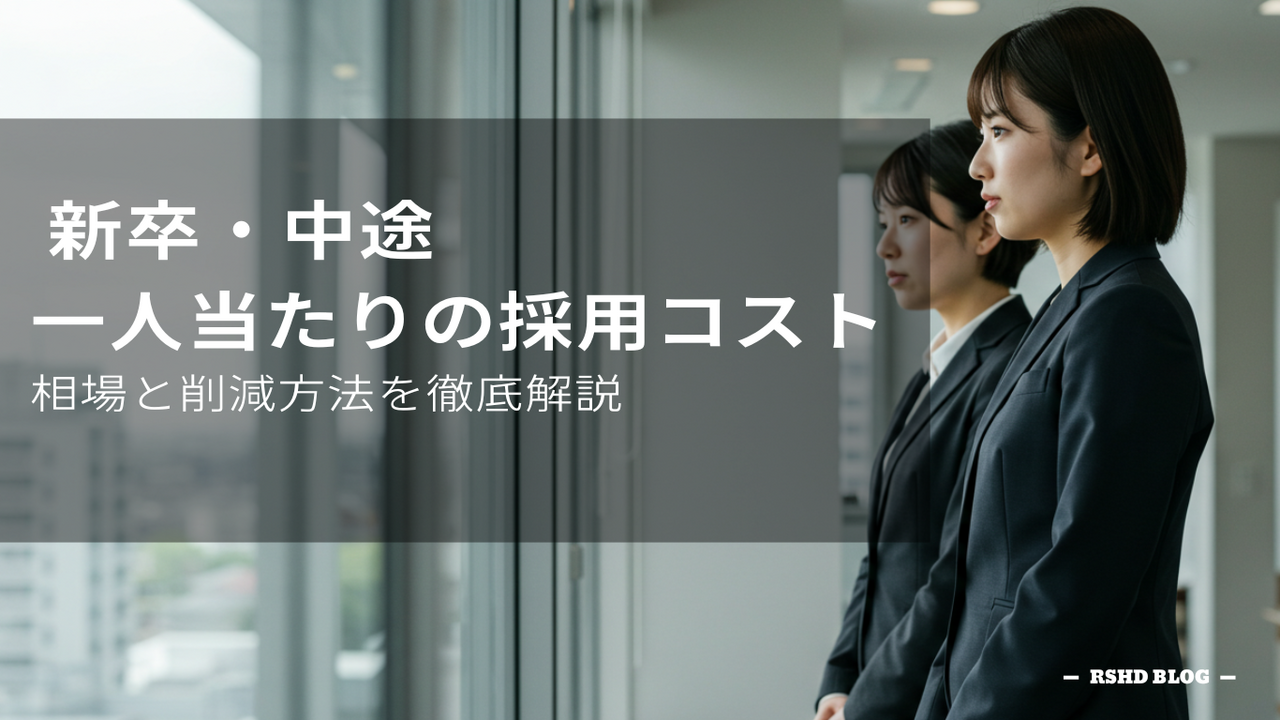
企業の持続的な成長と競争力の維持には、優秀な人材の確保が不可欠です。しかし、人材採用には相応のコストがかかるため、効果的な採用コスト管理が企業の人材戦略において重要な要素となっています。
本記事では、新卒・中途・アルバイトの採用コストの相場や計算方法、そしてコスト削減のポイントについて詳しく解説します。
目次
採用コストとは?
採用コストとは、採用に関わるコスト全般のことで求人広告費、面接にかかる人件費、採用イベントの開催費用、採用システムの導入・運用費など、採用にかかる経費はすべてのことです。
これらのコストは企業の規模や業界、採用手法によって大きく異なりますが、適切に管理することで効率的な採用活動が可能になります。
採用コストは「外部コスト」と「内部コスト」の2つに分類されます。
外部コスト
外部コストは、採用コストのうち外注のために発生した費用のことです。
例えば求人広告会社へ依頼し、求人広告を出す場合が分かりやすい例と言えるでしょう。さらには、人材紹介手数料や就職・転職の合同説明会にかかる費用なども外部コストに含まれます。
外部コストに含まれるもの
・求人広告の掲載費用
・企業説明会や面接の会場の利用料
・人材紹介会社に支払う成功報酬
・採用管理システム、オンライン面接に使うツールの利用料など
・採用サイト、パンフレットなど採用に使う印刷物などを外注した場合の費用
内部コスト
内部コストは、社内の採用業務にかかる費用全般のことです。面接官や採用担当者の人件費の割合が多くなります。
またセミナーや就職説明会などで、採用担当者や面接官などに発生する宿泊費や移動のための交通費なども内部コストに含まれます。
内部コストに含まれるもの
・採用担当者や面接官の人件費
・セミナーや就職説明会などの際に発生する交通費や宿泊費
・候補者への交通費
・リファラル採用のインセンティブ

採用コストの計算方法
採用コストを正確に把握するためには、適切な計算方法を用いる必要があります。ここでは、採用コストの計算方法について詳しく解説します。
一人当たりの採用コスト(採用単価)の計算方法
採用コストとは採用にかかった経費すべての合計のことを指しますが、一方で1人当たりの採用コストを「採用単価」と呼びます。
「採用コスト」と「採用単価」は若干意味合いが異なるので注意しましょう。この記事では「採用単価」と「一人当たりの採用コスト」を同じ意味で使っています。
一人当たりの採用コスト(採用単価)は、以下の式で計算できます。
採用単価 = 採用コストの総額(内部コスト + 外部コスト) ÷ 採用人数
例えば、採用コストの総額が1000万円で、10人を採用した場合、一人当たりの採用コストは100万円となります。
当然のことながら採用コストは企業規模や採用人数によって大きく異ってきます。会社規模が大きくなれば採用人数も多くなる傾向にあり、採用にかかる費用も大きくなっていきます。
そのため、自社のコストパフォーマンスを分析する際には採用単価を指標にするとよいでしょう。採用コストで見てしまうと比較や分析が難しい場合がありますが、一人当たりの採用コストで見れば、他社や前年度との比較がしやすくなるでしょう。
求人広告費用の計算方法
採用コストの中でも求人広告費にかかるコストを「求人広告費用」といいます。外部コストのうち求人広告にかかる費用が多くの割合をしめるケースも多いかと思いますが、求人広告費用の効果を測定していく際に有用な指標となります。
一人当たりの求人広告費用 = 求人広告費総額 ÷ 採用人数
この計算方法を用いることで、求人広告の効果をより詳細に評価することができます。

平均採用コストはどれくらい?
リクルート「就職白書2020」によると2019年度新卒採用および中途採用1人あたりの平均採用コストは以下の通りです。
19年度の新卒採用(20年卒):93.6万円
中途採用のコスト:103.3万円
1人あたりの平均採用コストは、 18年度の平均採用コスト (新卒採用71.5万円、 中途採用83.0万円)と 比べると、新卒、中途ともに増加 していることがわかります。
新卒平均採用コスト
リクルート「就職白書2020」(p.9, 10)によると2019年度の新卒採用では一人あたりの平均コストは93.6万円。18年度の平均コストが71.5万円だったことから増加傾向にあります。
この資料によると新卒採用を実施する上での課題の上位に「採用に係る人員数」などが挙げられたことが報告されており、内部コストが課題になっているケースが多いようです。
新卒採用は一度に多くの人材を採用できるため、1人あたりのコストは中途採用と比べて低くなる傾向があります。しかし、この数字は企業規模や業界によって大きく異なることに注意が必要です。
また、出典:マイナビ採用支援情報サイト サポネット「新卒採用の予算について」のデータをもとに内訳を計算すると新卒採用の採用コストの内訳は以下の通りとなりました。
広告費 46.97%
インターンシップ 15.64%
セミナー運用費 20.69%
内定後にかける費用 15.03%
その他 5.07%
新卒採用では、広告費が約半分を占め、また、インターシップや合同企業説明会や学内セミナーなどのイベント費用も大きな割合を占めていることのが特徴です。また、長期的な視点での人材育成が必要となるため、内定後の研修費用なども考慮に入れる必要があり、そのことが内定後に一定のコストをかけている様子からわかります。

中途採用コスト
リクルート「就職白書2020」(p.9, 10)によると中途採用の平均コストは、103.3万円となっています。
中途採用は即戦力の確保を目的とすることが多く、新卒採用よりもコストがかかる傾向にあります。これは、より専門的なスキルや経験を持つ人材を探す必要があるため、求人広告費や人材紹介会社への手数料が高くなることが主な要因です。
次に採用一人当たりの求人広告費をみてみましょう。
株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」(p.121)によると2023年に転職サイト、折り込み求人誌、新聞の求人欄、フリーペーパーなどでかかった採用一人当たりの求人広告費は以下の通りです。
求人広告費
全職種平均:38.5万円(前年比:4.8万円減)
その前の2年間の値は以下の通りでした。
求人広告費
2023年全体平均:38.5万円
2022年全体平均:43.3万円
2021年全体平均:37.3万円
業種別でみるとIT・通信・インターネットが52.9万円で最も高く、次いで金融・保険・コンサルティングが48.3万円。採用窓口エリア別では東京・南関東・近畿地方など大都市が多いエリアでの求人広告費が高めとなる傾向にある、と報告されています。
従業員規模別で見てみると以下の通りです。
3〜10名:21.4万円
51〜300名:40.4万円
301〜1,000名:35.9万円
1,001名以上:44.6万円
このように会社規模が大きくなればなるほど求人広告費がかかっていることが分かります。
中途採用では、人材紹介会社の利用が多いため、その手数料がコストになる場合も多いです。一般的に、年収の30%程度が相場となっています。また、専門性の高い職種では、より高額な手数料が発生することもあります。

アルバイト採用コスト
株式会社マイナビ「バイト通信・採用活動に関する最新調査データについて」(p.6)によると2022年のアルバイト1名あたりの採用単価は7.0万円となっています。
業種別でみると「保育」が11.2万円と最も高く「接客(ホテル・旅館)」が3.9万円と最も低い数字となっています。
それ以前の何年かの推移で見てみると
2022年:7.0万円
2021年:6.0万円
2020年:5.2万円
2019年:6.4万円
となっています。2020年に一旦減少したものの、その後は増加傾向にあることが分かります。
会社規模別でみると以下の通りです。
正社員数100人未満:5.7万円
正社員数100~299人:7.2万円
正社員数300~499人:10.1万円
正社員数500人以上:10.2万円
会社規模が大きいほどアルバイト1名あたりの採用単価は高くなる傾向にあるます。
アルバイト採用では、主にオンラインの求人サイトやSNSを活用することが多く、新聞や雑誌などの従来型メディアへの広告出稿は少なくなっています。また、面接プロセスも比較的シンプルで、1回の面接で採用を決定することが多いため、採用にかかる時間とコストを抑えることができます。
しかし、アルバイトの採用コストは一見低く見えますが、離職率が高い傾向にあるため、頻繁な採用活動が必要となる可能性があります。そのため、長期的な視点での採用コスト管理が重要となります。

アルバイト採用コスト削減事例
ロケットスタートホールディングがお手伝いさせて頂いた食品製造業のお客様の事例をご紹介します。
今までは食品製造で募集をかけていましたが、丁寧にヒアリングしたところ、一口に「製造」といっても、盛付、調理、加工といった工程に分かれていることがわかりました。
それぞれ別の求人をつくりラインごとに募集を行うことを提案。軽作業であることも仕事内容でしっかり伝えなおしました。Indeedの採用市場レポートで職種カテゴリを調査し、マーケットとズレがないことも確認した結果2週間に7万5000円の投資で応募10件中3名のご採用が決まりました。
1名あたりの単価にすると2週間で2.5万円の求人広告費ということになります。
このように工夫次第では採用コストは工夫次第で下げることができます。詳しくはこちらの記事をぜひ参考にしてみてください。
それ以外にもご参考にしていただける採用事例記事をたくさんご紹介しています。
採用コストの相場:企業規模別・職種別の比較
採用コストの相場は、企業の規模や採用する職種によって大きく異なります。ここでは、企業規模別・職種別の採用コスト相場を詳しく見ていきます。
企業規模別の採用コスト相場
株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」(p.121)によると2023年企業規模別の中途採用コストは以下のようになっています。
3〜10名:21.4万円
51〜300名:40.4万円
301〜1,000名:35.9万円
1,001名以上:44.6万円
大企業ほど採用予算が大きくなる傾向が見られますが、一人当たりの採用コストは必ずしも企業規模に比例するわけではありません。これは、大企業ほど採用活動の規模が大きくなり、スケールメリットが働くためです。

企業規模別の採用コストの特徴は以下の通りです。
1. 小規模企業(3~50人)
・採用予算が限られているため、効率的な採用活動が求められる
・社長や経営陣が直接採用に関わることが多い
・人材紹介会社の利用頻度が低く、自社での採用活動が中心
2. 中規模企業(51~300人)
・採用専門の担当者を置くことが増える
・求人広告や人材紹介会社の利用が増加
・採用システムの導入を検討し始める段階
3. 大規模企業(301~1000人)
・専門の採用部門を持つことが一般的
・多様な採用チャネルを活用
・採用システムの導入が進み、データ分析による採用戦略の最適化が行われる
4. 超大規模企業(1001人以上)
・大規模な採用キャンペーンや広告展開を行う
・独自の採用サイトやアプリを開発・運用
・AI技術を活用した採用プロセスの自動化が進む

職種別の採用コスト相場
職種によっても採用コストは大きく異なり、株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」(p.121)によると、中途求人広告費用の相場は以下の通りです。
| 職種 | 中途求人広告費用 |
|---|---|
| IT・通信・インターネット | 52.9万円 |
| メーカー | 39.9万円 |
| 商社 | 30.6万円 |
| サービス・レジャー | 39.1万円 |
| 医療・福祉・介護 | 32.6万円 |
| 流通・小売・フードサービス | 31.8万円 |
| マスコミ・広告・デザイン | 29.5万円 |
| 金融・保険・コンサルティング | 48.3万円 |
| 不動産・建設・設備・住宅関連 | 34.9万円 |
| 運輸・交通・物流・倉庫 | 30.5万円 |
| 環境・エネルギー | 26.3万円 |
| 公的機関 | 34.4万円 |
IT系やクリエイティブ系の職種は比較的高額な傾向にあります。これらの職種別採用コストの特徴を詳しく見ていきましょう。

1. 営業・事務系
・比較的安定した採用コスト
・求職者の母数が多いため、採用に要する時間が短い
・一般的なスキルセットで対応可能な場合が多い
2. サービス系
・採用コストは比較的低め
・アルバイトからの正社員登用も多い
・接客スキルや経験が重視される
3. 医療・教育系
・専門資格が必要なため、採用対象が限定される
・業界特化型の求人サイトや人材紹介会社の利用が多い
・地域によって採用難易度が大きく異なる
4. クリエイティブ系
・ポートフォリオの確認など、選考プロセスが複雑になりやすい
・フリーランスからの転職も多く、柔軟な雇用形態の提示が必要
・業界内のネットワークを活用した採用も多い
5. 金融・公共・IT系
・高度な専門知識やスキルが要求されるため、採用コストが高い
・グローバル人材の採用も多く、英語力などの追加要件がある
・最新技術に対応できる人材の獲得競争が激しい
6. その他技術職
・業界や必要なスキルセットによって採用コストに幅がある
・資格や経験年数によって採用難易度が大きく変わる
・業界特有の技術や知識が必要なため、採用に時間がかかることがある
これらの職種別の特徴を理解し、それぞれに適した採用戦略を立てることが重要です。例えば、IT系の採用では、技術コミュニティへの参加やハッカソンの開催など、従来の求人広告だけでなく、直接的なアプローチも効果的です。

応募者数と内定辞退者数から分析する採用コスト
2025年卒採用の見通し
「就職白書2024」データ集によると2025年卒採用では全体的には応募人数は減り、内定辞退者が増えるという見通しが立てられていました。
2024年卒採用と比較した2025年卒採用の内定辞退人数見通しは以下の表の通りとなっています。
2024年卒採用と比較した2025年卒採用の応募人数見通し
| 増える | 同じ | 減る | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 23.4% | 45.5% | 31.1% |
| 従業員規模別 | |||
| 300人未満 | 16.7% | 53.0% | 27.8% |
| 300〜999人 | 23.4% | 43.7% | 32.9% |
| 1000〜4999人 | 31.6% | 44.2% | 24.2% |
| 5000人以上 | 28.1% | 46.5% | 25.3% |
2024年卒採用と比較した2025年卒採用の内定辞退人数見通し
| 増える | 同じ | 減る | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 19.8% | 67.0% | 13.2% |
| 従業員規模別 | |||
| 300人未満 | 16.7% | 69.5% | 13.8% |
| 300〜999人 | 17.2% | 65.9% | 17.6% |
| 1000〜4999人 | 24.1% | 66.0% | 9.9% |
| 5000人以上 | 24.1% | 60.5% | 15.4% |
応募人数の見通しでは、「増える」と回答した企業が約2割、「同じ」が7割弱、「減る」が1割強となっており、多くの企業が現状維持または微増を見込んでいる状況です。
一方、内定辞退者数の見通しでは、「増える」と考える企業が約2割強、「同じ」とする企業が約半数、「減る」とする企業が3割強となっています。辞退者が増えると予想する企業(23.4%)が一定数存在する一方で、3割以上の企業が辞退者数の減少を見込んでおり、企業間で見解が分かれていることがわかります。
企業規模別の違い
応募人数の見通しでは、従業員数が多い企業ほど「増える」と回答する割合が高く、小規模企業ほどその割合が低い傾向にあります。大企業は知名度やブランド力により応募者数の増加を期待しやすい一方で、小規模企業では応募者の増加が見込みづらい状況にあると考えられます。
また、内定辞退者数の見通しにおいても、大企業ほど「増える」と考える割合が高くなっています。これは、大企業では応募が増える分、内定者の数も増加し、結果として辞退者も増えると予想されるためです。一方、小規模企業では辞退者が増えると予想する割合が比較的低く、応募者数が限られる分、採用活動を丁寧に行うことで辞退を減らせる可能性があると考えられます。
採用コストへの影響と対策
応募と内定辞退のギャップ
応募者数が多い一方で内定辞退率も高い場合、1人の内定を獲得するために多くのリソースが必要となります。その結果、採用コストが上昇する要因となります。
企業規模による違い
大企業は知名度が高いため応募者が多く集まりやすいものの、その分内定辞退の割合も高くなる傾向があります。一方、中小企業はそもそもの応募者数が少ないため、採用の母数が限られています。どちらの企業規模でも、効率的な選考を行わなければ1人あたりの採用コストが高くなってしまいます。
再採用のリスク
内定辞退が多発すると、すでに投資した採用活動のコストが無駄になるだけでなく、新たに採用活動を実施する必要が生じます。その結果、全体の採用コストがさらに増加する可能性があります。
大企業の課題:
応募者が増える一方で、内定辞退者も増加する可能性があるため、早期の動機付けや内定後のフォローを強化することが重要です。
中小企業の課題:
大企業ほど応募者の増加が見込めないため、自社の魅力を効果的に伝え、ミスマッチを防ぐ工夫が必要です。また、辞退者を減らすための選考プロセスの見直しや、内定後のフォロー体制の充実が求められます。
採用コスト削減のポイント
採用コストを効果的に削減するためには、様々な方策を検討する必要があります。ここでは、採用コスト削減のポイントについて詳しく解説します。
ミスマッチの防止(内定辞退・早期離職の防止)
社員の早期離職は企業にとって大きな損失です。新卒でも中途でも、一人あたりの採用コストとして約100万円前後が掛かってきますが、入社に至るまでに費やした時間と費用、入社後の各種手続きや研修などでかかった人件費や給与など、せっかくの投資が無駄になってしまいます。
特に採用コストを多くかけられない中小企業にとっては大きな痛手であり、ミスマッチを防ぐ工夫が求められます。
早期退職の主な原因は、入社前の期待と入社後の現実とのギャップであることが多いです。たとえば、事前に聞いていた情報と異なる、働き方が合わない、同僚との相性が良くないなど、仕事の内容、労働環境、人間関係におけるミスマッチが理由です。このため、書類選考や面接の段階で、自社との相性が良い人材をしっかり見極めることが重要です。
さらに、内定辞退が起こると、これまで投資した採用コストが無駄になるため、内定者が辞退を考える原因となる「事前情報とのギャップ」を防ぐ工夫が必要です。説明会や面接で伝えた内容と、内定後の企業の対応に大きな差があると、内定辞退の確率が高まります。これを防ぐには、関係者間での情報の共有が必要で、また、企業の長所だけでなく、実際の状況や課題も含めた説明が効果的です。
さらに、ミスマッチを避けるためには「カジュアル面談」を取り入れて、相互の認識をすり合わせる機会を設けることもできるでしょう。カジュアル面談とは、合否関係なく採用担当者や現場社員が求職者と率直に情報交換する場を指します。求職者の経歴やキャリアプラン、企業が求める職種の仕事内容、さらには求職者の価値観など深い部分まで情報を交換することで、ミスマッチを軽減できます。
通常の選考過程では求職者は本音を言いにくい傾向があるため、選考と無関係の場を設けることが早期退職を防ぐ対策策の一つになります。
他には、インターンシップ制度やOG面談を通じて、内定者と企業の距離を縮める仕組みを導入する方法も考えられます。これらの対策を通じてミスマッチを防ぎ、早期退職を減らすことが可能です。

■ ポイント
早期離職の損失:
企業にとって社員の早期離職は大きな損失であり、採用コスト(約100万円)が無駄になる。
中小企業への影響:
中小企業は採用コストを多くかけられないため、早期離職が特に痛手となる。
早期退職の原因:
事前の期待と入社後の現実のギャップが主な原因(仕事内容、働き方、労働環境、人間関係のミスマッチ)。
ミスマッチ防止の工夫:
書類選考や面接段階で、自社との相性が良い人材を見極めることが重要。
内定辞退防止:
内定後の対応と説明内容にギャップがないようにし、関係者間で情報を共有し、実際の状況や課題を説明する。
カジュアル面談の導入:
求職者と率直な情報交換を行い、相互の認識をすり合わせることでミスマッチを減らす。
インターンシップやOG面談:
内定者と企業の距離を縮めるためにインターンシップやOG面談を活用。
ミスマッチ防止の効果:
これらの対策を通じて、早期退職を減らすことが可能。
自社の採用サイトの活用
自社の採用ページを活用した採用活動は、求人広告媒体に依存するよりも採用コストを大幅に削減できる手段として注目されています。
特に、知名度の高い企業であれば自社ページへのアクセスが期待でき、効果的な採用方法と言えるでしょう。また、自社の採用サイトは求人媒体とは異なり、情報掲載の自由度が高く、求職者に対して企業のビジョン、社風、仕事内容、労働条件などを詳細に伝えられるメリットがあります。
しかし、自社の採用ページ強化には、サイトのリニューアルや運営費用、社内担当者の人件費といった初期投資が伴います。
そのため、単年度でのコスト削減を期待するのではなく、中長期的な視点で計画的に強化を進めていくことが重要です。まずは、求職者が求める情報が自社ページに確実に盛り込まれているかを確認しながら、必要な改善を進めていくことが求められます。
■ ポイント
・自社の採用ページは求人広告媒体に依存せず、採用コストを削減できる。
・ 特に知名度の高い企業は自社ページへのアクセスが期待でき、効果的な採用手段となる。
・初期投資が必要なため、中長期的な視点で計画的に強化を進め、求職者に必要な情報を提供することが重要。
求人媒体の見直し
高額な費用を支払っているにも関わらず、応募が全くない場合、求人媒体と自社の採用ニーズとの間にミスマッチがある可能性があります。自社が求めている人材が利用している求人媒体に十分登録されているかを確認し、もし少ない場合は別の媒体に切り替えることが必要です。
また、職種によっては特定の時期に求職者の動きが活発になることがあるため、そのタイミングを見計らって募集をかけることも重要です。
さらに、求人広告はシーズンごとにキャンペーンや特別割引が適用されることがあり、費用が変動しやすいです。また、広告費用は数十万~百万円単位の大きな金額が動くため、あれこれ手を広げて無駄に掲載するとコストが増加してしまいます。
広告媒体ごとの費用対効果を冷静に計算し、必要に応じて見直しを行うことをおすすめします。
リファラル採用
リファラル採用は、社員に友人や知人を紹介してもらい、採用候補者を集める方法です。リファラル採用は縁故採用と異なり、合否を伴う選考が行われます。候補者と企業の間で事前に調整を行った上で入社することができます
このアプローチでは、外部の広告費用や求人サイトへの掲載費用が不要で、採用コストを大幅に削減することができます。
社員から紹介を受けるため、候補者は既に働いている社員から職場のリアルな情報を聞けるため、通常の採用方法に比べてマッチング率が高くなる傾向があります。そのため早期離職のリスクを減らすことができます。
発生するコストは、紹介してくれた社員へのインセンティブが主で、数万円から数十万円程度が相場ですが、人材紹介サービスを利用するよりも低コストで済むのが特徴です。
リファラル採用を強化するためには、社員が紹介しやすくなる仕組み作りが必要です。例えば、紹介カードの作成やインセンティブの導入が有効です。しかし、インセンティブを過剰に設定すると、内部コストが膨らんでしまう可能性があるため、従業員エンゲージメントを高め、社内環境を整えることが重要です。

SNSやオウンドメディアの活用
SNSやオウンドメディアを活用することで、低コストで効果的な採用活動が可能になります。
・ソーシャルリクルーティング:SNSを活用した採用手法
LinkedIn、Twitter、Facebookなどのプラットフォームを活用し、直接求職者とコンタクトを取ります。
・オウンドメディアリクルーティング:自社の採用サイトやSNSアカウントを活用した採用手法
自社の魅力や社員の声を発信し、企業ブランディングと採用活動を同時に行います。
・従業員によるSNS発信の促進
社員自身がSNSで会社の魅力を発信することで、より信頼性の高い情報発信が可能になります。
・コンテンツマーケティングの活用
業界トレンドや専門知識に関する記事を公開し、潜在的な求職者の関心を引きつけます。
・バーチャル企業説明会の開催
オンラインイベントを通じて、より多くの求職者にリーチすることができます。
・インフルエンサーマーケティング
業界内で影響力のある人物と協力し、採用ブランディングを強化します。
これらの手法を活用することで、求人広告費用を抑えつつ、自社の魅力を直接求職者に伝えることができます。

ダイレクトリクルーティングの活用
ダイレクトリクルーティングは、求職者データベースから直接スカウトする採用方法です。この手法には以下のメリットがあります。
・紹介会社経由では出会えない人材との接点を持てる
・自社にマッチした人材を効率的に探すことができる
・中途採用(キャリア採用)の即戦力枠での採用に効果的
ダイレクトリクルーティングを効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。
・明確なターゲット設定
求める人材のプロフィールを具体的に定義し、効率的な検索を行います。
・パーソナライズされたアプローチ
候補者の経歴や興味関心に基づいて、個別化されたメッセージを送ります。
・タイミングの最適化
候補者の状況や業界の動向を考慮し、適切なタイミングでアプローチします。
・継続的なリレーションシップ構築
即時の採用に至らなくても、長期的な関係性を築くことで、将来の採用につなげます。
・採用担当者のスキル向上
効果的なメッセージの書き方や交渉スキルなど、ダイレクトリクルーティングに特化したスキルを磨きます。

内部コストの見直し
採用活動における内部コストの大部分は人件費です。以下の点を見直すことで、コスト削減につながる可能性があります。
・採用業務のマニュアル整備
標準化されたプロセスを確立し、効率的な採用活動を実現します。
・業務効率の見直し
不要な会議や重複した作業を削減し、採用担当者の生産性を向上させます。
・リファラル採用(社員紹介制度)の活用
既存社員のネットワークを活用することで、質の高い候補者を低コストで獲得できます。
・採用プロセスの自動化
応募者の一次スクリーニングやスケジュール調整などを自動化し、人的コストを削減します。
・クロスファンクショナルな採用チームの構築
人事部門だけでなく、各部門の社員も採用活動に参加することで、より効果的な評価が可能になります。
・採用KPIの設定と定期的な見直し
採用コスト、採用リードタイム、定着率などのKPIを設定し、継続的に改善を図ります。

採用代行の利用
採用代行サービス(または採用アウトソーシング)は、企業の採用業務を外部の専門家に委託することで、コスト削減と業務効率化を図る方法の一つです。このサービスを利用することで、採用にかかる工数や人手不足の問題が解消され、企業はコア業務に集中できるという利点があります。
採用代行サービスには「総合系」、「コンサル系」、「特化系」といった異なるタイプが存在し、各タイプがそれぞれ専門的なノウハウを保持しています。これらのプロ組織は、企業の予算内で効果的な採用活動をサポートし、過去の採用コストと比較しながら、効率的にサービスを活用することを推奨します。
ただし、すべての採用業務を一括して外注すると、自社内に採用ノウハウが蓄積されないというデメリットがあるため、どの範囲を委託するかは慎重な検討が必要です。予算と必要なサポートを確認しながら、自社のニーズに合わせた採用代行サービスの利用を検討すると良いでしょう。
採用代行(RPO)についてはこちらの「採用代行(RPO)とは?メリットと導入方法を徹底解説」の記事で詳しくご説明しました。
採用コスト削減に役立つサービス
採用コスト削減に有効なサービスをご紹介します。コスト削減を最優先に考える場合、会社の魅力や仕事のやりがいを強調できるサービスを選ぶことをお勧めします。
最近では、仕事のやりがいや職場環境に重きを置いて転職活動を行う人が増えているからです。掲載費用を抑えながら、金銭面以上に企業の理念やミッションといった思いの部分でつながれるような採用方法も検討してみてください。
Indeed(インディード)
Indeedは、毎月2.5億人が利用する求人掲載サイトで、企業がコストを抑えて採用活動を行うための最適なプラットフォームです。求人情報は、新規掲載や企業の採用ウェブサイト、各種採用管理システムから無料で表示できます。ただし、無料掲載の場合は自然と表示順位が下がるため、定期的に情報を更新したり、有料プランの活用を検討することが重要です。有料のスポンサー求人広告はクリックされた時点で課金され、無料求人と比較してクリック率が最大3.5倍向上する可能性があります。
また、Indeedは「キーワード」と「勤務地」という2つの検索窓を持ち、親和性の高い求人情報を検索結果として表示します。クリック課金型の仕組みのため、求人が閲覧されるまでは費用が発生せず、効率的な採用とコスト削減が可能です。求職者に見つけてもらう確率を高めたい企業は、露出を増やす有料プランの利用も検討してみてください。
そんなIndeedですが、Indeedの掲載料の仕組みがわかりにくいと感じておられる方も多いはず。こちらの「Indeedの掲載料は?:仕組みや効果的な求人掲載戦略を解説」の記事では掲載料の仕組みを詳しくご紹介しました。
Green(グリーン)
Greenは、IT・Web領域の経験者採用に特化した成果報酬型の求人メディアです。主にエンジニアやデザイナーの採用に強みを持ち、多くの登録者が20代から30代の若手層で構成されています。成功報酬は地域一律で30万〜90万円の固定金額であり、掲載期間が無期限なため、ランニングコストを抑えながら採用活動を行うことができます。
Greenの登録者の60%以上がIT・Web系の経験者であり、特に第二新卒やポテンシャルの高い若手層の採用に適しています。プロのライターとカメラマンが、企業の価値観や仕事の魅力を伝えるオリジナル記事を作成してくれるため、より効果的な人材獲得が期待できます。
さらに豊富な登録者データベースから、自社の求める人材を検索し、直接アプローチできるダイレクトリクルーティングが可能です。掲載求人数に制限がなく、いつでも情報の編集や新しい求人の追加ができるため、柔軟な採用戦略を展開できます。IT・Web領域での採用コストを抑えつつ効果的に強化したい企業には、Greenのサービスが最適です。
BizReach(ビズリーチ)
BizReach(ビズリーチ)は、日本最大級の人材データベースから、企業が自分で「欲しい」人材を探して直接スカウトできるサービスです。2024年3月末時点で、227万人以上の優れた人材が登録しており、経営幹部や管理職、専門職といった次世代のリーダーを含む多様な専門家が集まっています。これにより、さまざまな職種や業種の優秀な人材と出会えるチャンスがあります。
BizReachの特徴としては、独自の審査を通過した即戦力となる人材のみが登録している点が挙げられます。このため、企業はヘッドハンターや人材紹介会社が公開している国内最大級の即戦力人材データベースを直接検索でき、書類選考や面談でのミスマッチを減らすことが可能です。
まとめ:効果的な採用コスト管理のために
採用コストの削減は、単に費用を抑えるだけでなく、質の高い人材を効率的に採用することを目指すべきです。本記事で紹介した方法やサービスを参考に、自社に最適な採用戦略を構築してください。ここで重要なのは、コスト削減と採用の質のバランスを取ることです。過度なコスト削減は、優秀な人材の獲得機会を逃す可能性があります。一方で、効果的なコスト管理は、限られたリソースを最大限に活用し、より戦略的な採用活動を可能にします。
適切な採用コスト管理は、企業の持続的な成長と競争力の維持につながります。これは、優秀な人材の獲得が企業の成長エンジンとなるためです。適切なコスト管理により、必要な人材を必要なタイミングで採用することが可能となり、ビジネスの機会損失を防ぐことができます。また、効率的な採用プロセスは、候補者体験の向上にもつながり、企業ブランディングにも好影響を与えます。
常に市場動向や自社の採用ニーズを把握し、柔軟に採用戦略を調整していくことが重要です。労働市場は常に変化しており、新たな技術やスキルセットの需要が生まれる一方で、従来の職種が陳腐化することもあります。このような変化に対応するためには、定期的な市場調査や自社の人材ニーズの分析が欠かせません。

また、競合他社の採用動向や業界全体のトレンドにも注目し、自社の採用戦略に反映させていく必要があります。
採用コストだけでなく、採用の質や速度、候補者体験なども総合的に考慮し、バランスの取れた採用活動を心がけましょう。採用の質を高めるためには、明確な評価基準の設定や、構造化面接の導入などが効果的です。
採用速度の向上には、採用プロセスの効率化やAIツールの活用が有効です。候補者体験の改善には、迅速なフィードバックや透明性の高いコミュニケーションが重要です。これらの要素を総合的に最適化することで、コスト効率の高い採用活動が実現できます。
採用コスト管理は一度行えば終わりではなく、継続的な改善が必要なプロセスです。定期的に採用活動の効果を測定し、PDCAサイクルを回すことで、より効率的で効果的な採用活動を実現することができます。具体的には、以下のようなステップを踏むことをおすすめします。
1. Plan(計画):採用目標と予算を設定し、具体的な施策を立案する
2. Do(実行):計画に基づいて採用活動を実施する
3. Check(評価):採用コスト、採用数、定着率などの指標を分析する
4. Act(改善):分析結果に基づいて、次の採用計画を改善する
このサイクルを継続的に回すことで、採用活動の効率と効果を段階的に向上させることができます。

また、採用コスト管理の効果を最大化するためには、採用部門だけでなく、経営層や各事業部門との連携も重要です。採用計画を経営戦略と整合させることで、より戦略的な人材獲得が可能になります。同時に、各部門のニーズを正確に把握することで、ミスマッチを防ぎ、採用後の定着率向上にもつながります。
常に最新の採用トレンドや技術動向にアンテナを張り、自社の採用戦略を進化させ続けることが、長期的な成功につながるのです。例えば、AIを活用した候補者スクリーニングや、VR技術を用いた職場体験など、新しいテクノロジーの導入を検討することも有効です。ただし、新技術の導入に当たっては、コストと効果のバランスを十分に検討し、段階的に導入していくことが賢明です。
最後に、採用コスト管理は単なるコスト削減ではなく、企業の成長戦略の一環として捉えることが重要です。適切な採用コスト管理により、必要な人材を適切なタイミングで獲得し、企業の持続的な成長を支える基盤を築くことができます。
本記事で紹介した様々な手法やツールを活用をお考えの際は、是非ロケットスタートまでお気軽にご相談ください。

高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ
お客様も気づかなかったベストマッチを
人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。
会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。
そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。
「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて
また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。
でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。
圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで
ロケットスタートホールディングスは、IndeedシルバーパートナーとしてIndeed/Indeed PLUSを活用した採用成功への伴走支援(採用エンジン)を行っております。

※ IndeedシルバーパートナーはIndeedの定めた正規認定パートナーの証しです。
採用エンジンについてもっと詳しく知りたい方は下記バナーをクリック!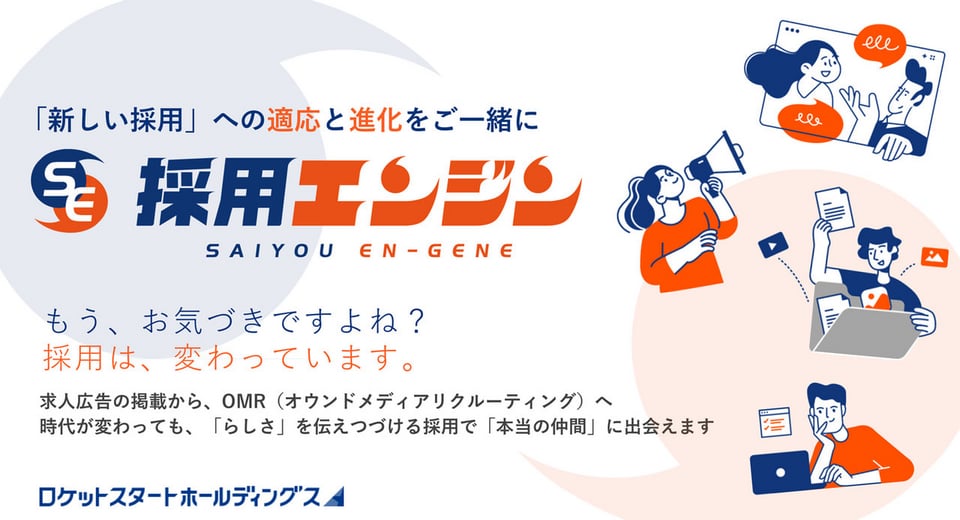
地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様に最適なプランを1社1社丁寧にご提案いたします。最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。
一覧へ戻る